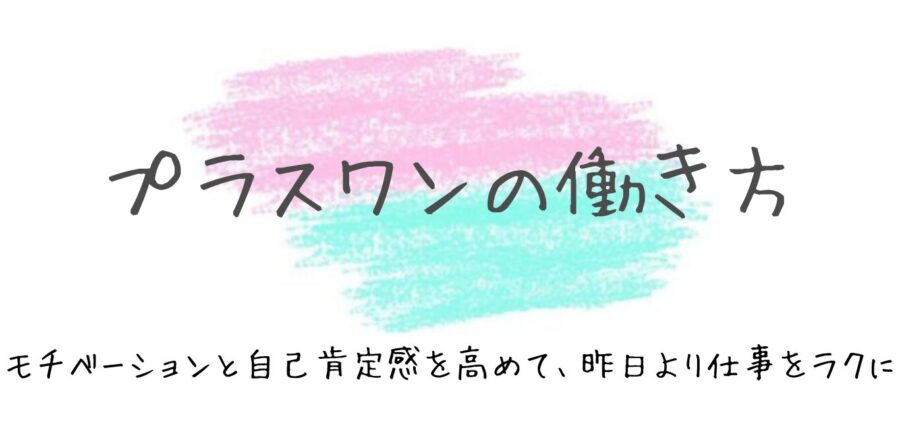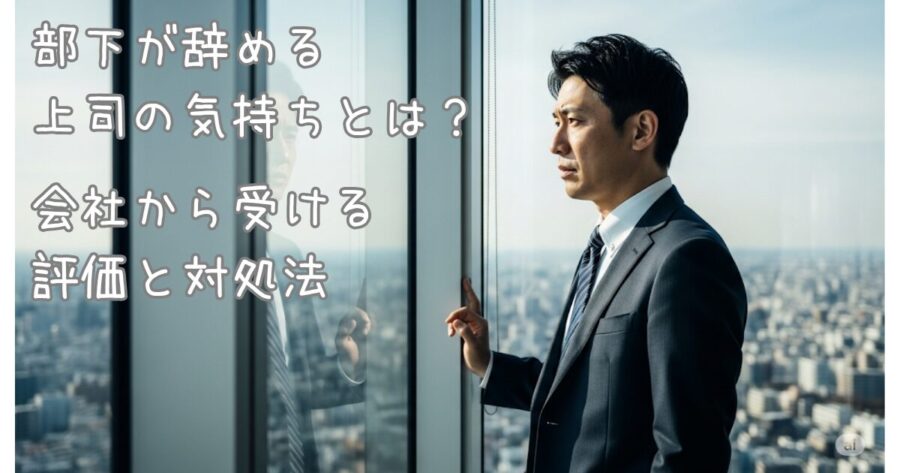「手塩にかけて育てた部下が、突然『辞めます』と…」 「部下の離職が続くと、自分の評価はどうなるんだろう…」
管理職としてチームを率いる中で、部下の離職は最も心をえぐられる出来事の一つではないでしょうか。
衝撃、焦り、そして「自分の何がいけなかったんだ?」という自責の念。チームの戦力がダウンする現実的な問題に加え、やり場のない感情に苛まれ、眠れない夜を過ごしている方もいらっしゃるかもしれません。
ご安心ください。その悩みは、あなた一人だけが抱えているものではありません。この記事では、多くの管理職が経験する部下退職のリアルな気持ちと、それが人事評価に与えるシビアな影響について、国や企業の公的なデータを基に徹底的に解説します。
さらに、この危機的な状況を乗り越え、**「部下が辞めない最強のチーム」**を築くための具体的なアクションプランまで、網羅的にご紹介します。
この記事を読み終える頃には、あなたは部下の離職に対する漠然とした不安から解放され、明日から何をすべきかが明確になっているはずです。
部下が辞める上司の気持ちとは?評価に与える影響と残酷な現実
- 突然の退職報告にショック…上司が感じる孤独と喪失感
- 「自分のせいだ」部下退職で自分を責めてしまう上司の心理とは
- なぜ優秀な部下ほど相談せず辞めるのか?その本当の理由とは
- 知らずにやっている…部下が辞める上司のNG行動ワースト5
- 部下が辞めると上司の評価はどうなる?会社のシビアな判断とは
- 後任不在で大混乱…部下が辞めた後の上司の末路
- なぜ部下は退職理由を言わない?隠されたホンネの見抜き方
突然の退職報告にショック…上司が感じる孤独と喪失感

部下からの「辞めたいです」という一言は、上司の心に深く突き刺さります。特に、期待をかけ、熱心に指導してきた部下であればあるほど、その衝撃は計り知れません。まるで、大切に育ててきた我が子に突然別れを告げられたかのような、強い喪失感に襲われることでしょう。
✅ 裏切られたような気持ち 信頼関係を築けていると思っていた部下からの突然の報告は、「なぜ一言も相談してくれなかったんだ」という、裏切られたような気持ちを生むことがあります。日々の業務で忙殺される中、部下の小さなサインを見逃していた自分を責め、「自分は上司として信頼されていなかったのか」と孤独感を深めてしまうのです。
✅ チームの今後への強い不安 感情的なショックと同時に、現実的な問題が一気に押し寄せます。「残されたメンバーで業務は回るのか」「後任はすぐに見つかるのか」「プロジェクトの納期は大丈夫か」。これらのプレッシャーは、管理職に重くのしかかります。特に、中間管理職は経営層と現場の板挟みになりやすく、その心労は計り知れません。実際に、株式会社ジェイフィールが行った調査では、**中間管理職の6割以上が「職場で孤独を感じる」**と回答しており、部下の離職がその孤独感をさらに加速させる要因となり得ます。
ある日、エースとして期待していた部下から退職の意向を伝えられました。頭が真っ白になり、言葉が出ませんでした。彼とは何度も面談を重ね、キャリアプランも一緒に考えてきたつもりでした。それなのに、なぜ…。その夜は、悔しさと情けなさで一睡もできませんでした。チームのメンバーにどう説明すればいいのか、自分の無力さを痛感し、会社に行くのが怖くなったことを今でも覚えています。 (引用元:X(旧Twitter))
このように、部下の退職は単なる人員の欠員ではなく、上司の心に深い傷を残し、リーダーとしての自信を根底から揺るがす出来事なのです。このどうしようもない感情と向き合うことは、非常に辛いプロセスですが、まずはその気持ちを自分自身が受け止めることが、次の一歩を踏み出すためのスタートラインとなります。
「自分のせいだ」部下退職で自分を責めてしまう上司の心理とは
部下の退職を前にして、「自分のマネジメントが悪かったからだ」「もっと良い上司だったら、彼は辞めなかったはずだ」と、すべての原因を自分にあると考えてしまう管理職は少なくありません。この自責の念は、真面目で責任感の強い人ほど陥りやすい心理状態と言えるでしょう。
この背景には、いくつかの心理的な要因が考えられます。
- 責任感の強さ: チームの成果や部下の成長に責任を感じるあまり、部下の離職というネガティブな結果を、すべて自分の責任として抱え込んでしまう傾向があります。
- 完璧主義: 「上司として完璧でなければならない」という思い込みが強いと、部下の離職を自らの「失敗」と捉え、過度に自分を責めてしまいます。
- コントロール欲求: チームの状況をすべて自分の管理下に置きたいという欲求が強い場合、部下の離職というコントロール外の出来事に対して、無力感と罪悪感を抱きやすくなります。
しかし、本当に部下の離職は、100%上司だけの責任なのでしょうか?
株式会社リクルートの就職みらい研究所が発表した「就職白書2024」によると、学生が就職先を確定する際に決め手となった項目として、「自らの成長が期待できる」が最も多く挙げられています。これは、現代の若者がキャリア形成において「成長機会」を非常に重視していることの表れです。もし、会社の事業構造や本人のキャリアプランとの間にズレが生じていれば、それは上司一人の力ではどうにもならないケースもあるのです。
前職を辞めた時、直属の上司は「俺の力不足で申し訳ない」と何度も頭を下げてくれました。でも、本当の理由は会社の将来性への不安と、もっと専門性を高められる環境に行きたかったから。上司はすごく良い人だったし、感謝しかない。だからこそ、本当のことは言えなかった。上司のせいじゃないのに、申し訳ない気持ちでいっぱいでした。 (引用元:X(旧Twitter))
この体験談からも分かるように、部下が抱える退職の理由は、必ずしも上司との人間関係だけではありません。給与や待遇、労働環境、本人のキャリアプラン、会社の将来性など、様々な要因が複雑に絡み合っています。
もちろん、上司の言動が引き金になるケースも多々あります。しかし、すべてを「自分のせいだ」と抱え込むことは、精神的な健康を損なうだけでなく、問題の本質を見誤らせる危険性があります。まずは一旦冷静になり、**「自分にコントロールできること」と「自分にはコントロールできないこと」**を切り分けて考えることが、建設的な解決策を見出すための第一歩となるのです。
なぜ優秀な部下ほど相談せず辞めるのか?その本当の理由とは

「あいつなら、何かあれば相談してくれると思っていたのに…」 特に優秀で、自律的に仕事を進められる部下ほど、退職の相談をせずに突然辞表を提出するケースは後を絶ちません。上司としては、信頼していただけにショックも大きく、「なぜ一言も…」と悩んでしまうことでしょう。しかし、彼らが相談しないのには、明確な理由が存在します。
優秀な人材が「相談」というステップを飛ばす最大の理由は、「相談しても無駄だ」と判断しているからです。彼らは、現状の問題が上司や会社の方針に起因する構造的なものであり、一個人の相談では解決不可能だと、冷静に分析していることが多いのです。
厚生労働省が発表した「令和4年雇用動向調査結果の概況」を見ると、若年層の離職理由が浮き彫りになります。
【転職入職者が前職を辞めた理由(男性)】
| 順位 | 25~29歳の離職理由 | 30~34歳の離職理由 |
|---|---|---|
| 1位 | 仕事の内容に興味を持てなかった(14.1%) | 給料等収入が少なかった(14.1%) |
| 2位 | 会社の将来が不安だった(12.3%) | 労働時間、休日等の労働条件が悪かった(11.0%) |
| 3位 | 労働時間、休日等の労働条件が悪かった(11.4%) | 会社の将来が不安だった(10.6%) |
※出典:厚生労働省「令和4年雇用動向調査結果の概況」
このデータから分かるように、「給料」「労働条件」「会社の将来性」といった項目は、上司個人の裁量で解決するには限界があります。優秀な部下は、これらの構造的な問題を敏感に察知し、「上司に相談して気まずくなるよりも、次のステージを探した方が合理的だ」と判断するのです。
さらに、優秀な人材には以下のような特徴も見られます。
- 見切りが早い: 問題解決能力が高いがゆえに、解決不可能な問題に対する見切りも早くなります。「この環境で悩み続ける時間は無駄だ」と判断し、迅速に次の行動に移します。
- 引き止めを迷惑だと感じる: 自分の決断に責任を持っており、上司に相談することで引き止められることを「余計な情に訴えられる時間」と感じ、避ける傾向があります。
- 既に次のキャリアプランがある: 常に自身の市場価値を意識しており、転職活動を水面下で進め、次の就職先が決まってから報告するケースがほとんどです。
つまり、彼らが相談しないのは、あなたを嫌っているからでも、信頼していないからでもありません。むしろ、あなたに迷惑をかけたくない、無駄な時間を使わせたくないという、彼らなりの配慮である可能性すらあるのです。この事実を理解することは、上司としての無用な自己嫌悪を防ぎ、より本質的な組織課題に目を向けるきっかけとなるでしょう。
知らずにやっている…部下が辞める上司のNG行動ワースト5
部下の退職は様々な要因が絡み合いますが、上司の日常的な言動が「最後の引き金」になるケースは非常に多いものです。良かれと思ってやっていることが、実は部下の心を静かに蝕んでいるかもしれません。ここでは、多くの管理職が知らずにやってしまいがちな、部下の離職に繋がるNG行動ワースト5をご紹介します。
第1位:部下の手柄を横取りする、自分の手柄のように話す これは信頼関係を根底から破壊する、最もやってはいけない行為です。部下が努力して出した成果を、まるで自分がやったかのように上層部に報告したり、会議で発表したりする。本人は巧妙にやっているつもりでも、部下は必ず気づいています。正当な評価を受けられない環境では、働く意欲が湧くはずがありません。
第2位:人によって態度をコロコロ変える(えこひいき) お気に入りの部下には優しく、そうでない部下には厳しい。あるいは、自分の機嫌次第で言うことが変わる。このような態度は、チーム内に深刻な不公平感を生み出します。「頑張っても、あの上司には評価されない」と感じた部下は、モチベーションを失い、静かに会社を去る準備を始めるでしょう。
第3位:「昔はこうだった」と自分の価値観を押し付ける 「俺の若い頃は、終電まで働くなんて当たり前だった」「まずは言われたことをやれ」。このような過去の武勇伝や価値観の押し付けは、若手社員にとって最も響かない言葉です。時代背景も働く価値観も大きく変化していることを理解せず、自分の成功体験だけを振りかざす上司の下では、部下は息苦しさを感じるだけです。
第4位:具体的な指示やフィードバックをせず、精神論で片付ける 「もっと気合を入れろ」「プロ意識が足りない」。部下が壁にぶつかっている時、このような曖昧な精神論は何の解決にもなりません。部下が求めているのは、具体的な改善策や的確なフィードバックです。育成を放棄し、部下の成長に無関心な姿勢は、「この人からは何も学べない」という見切りに繋がります。
第5位:マイクロマネジメントで部下を縛り付ける 部下の仕事の進め方に対して、過度に細かく口を出し、すべてを管理しようとする行為です。これは一見、熱心な指導に見えるかもしれませんが、部下からすれば「信用されていない」と感じるだけ。裁量権を奪われ、自律的に働く機会を失った部下は、窮屈さを感じ、もっと自由に働ける環境を求めて去っていきます。
これらの行動に、一つでも心当たりはなかったでしょうか。重要なのは、これらの多くが上司の無意識のうちに行われているということです。一度、自身の普段の言動を客観的に振り返ってみることが、部下の離職を防ぐための重要な一歩となります。
部下が辞めると上司の評価はどうなる?会社のシビアな判断とは

「部下が一人辞めたくらいで、自分の評価は変わらないだろう」 もし、あなたがそう考えているなら、その認識は改める必要があるかもしれません。現代の企業において、部下の離職は、管理職の人事評価に直接的な影響を与える重大な問題として扱われるようになっています。
結論から言うと、部下の離職が続けば、あなたの管理職としての評価は間違いなく下がります。 場合によっては、降格や減給といった厳しいペナルティに繋がる可能性も否定できません。
なぜなら、現代の企業経営において「人材の定着(リテンション)」は最重要課題の一つだからです。一人の社員が辞めることによる損失は、単に欠員を補充するための採用コストや教育コストだけではありません。
- チームの生産性低下: 業務ノウハウが失われ、残されたメンバーの負担が増大する。
- 士気の低下: 「このチームは大丈夫か?」という不安が広がり、他のメンバーの離職を誘発する。
- 見えないコスト: 失われたビジネスチャンスや、顧客からの信頼低下など、数字に表れない損失も大きい。
これらの損失を防ぐことが、管理職の重要な責務であると、会社は考えています。そのため、多くの企業では、管理職の評価項目に以下のような指標を組み込んでいます。
✅ チームの離職率 ✅ 従業員エンゲージメントスコア ✅ 1on1ミーティングの実施率や質 ✅ 部下の育成計画の達成度
つまり、「目標数字を達成していれば良い」という時代は終わり、**「部下を育て、定着させ、チームとして継続的に成果を出せるか」**という点が、管理職の能力を測る上で極めて重要なものさしになっているのです。
部下の離職は、もはや「仕方がないこと」では済まされません。それは、あなたのマネジメント能力に対する会社からの**「危険信号」**であり、評価を下げる明確な根拠となる、という厳しい現実を直視する必要があるのです。
後任不在で大混乱…部下が辞めた後の上司の末路

部下が一人辞める。その影響は、上司の評価ダウンだけにとどまりません。特に、後任がすぐに見つからなかった場合、その上司とチームは想像以上に悲惨な状況に追い込まれることになります。これは、管理職としてのキャリアを揺るがしかねない、深刻な事態の始まりです。
1. 終わらないプレイングマネージャー化 まず直面するのが、辞めた部下の業務を誰かがカバーしなければならないという現実です。多くの場合、その穴を埋めるのは上司であるあなた自身。本来のマネジメント業務に加えて、膨大な実務がのしかかり、プレイングマネージャーとして疲弊していくことになります。自分の仕事は常に後回しになり、残業や休日出勤が常態化。心身ともに余裕がなくなり、他の部下へのケアも疎かになるという悪循環に陥ります。
2. チーム崩壊のドミノ倒し 上司が自分の業務で手一杯になると、チーム全体に歪みが生じ始めます。
- 残されたメンバーの負担増: 辞めた人の仕事が他のメンバーに振り分けられ、一人当たりの業務量が激増。不満が募り、エンゲージメントが著しく低下します。
- コミュニケーションの希薄化: 上司に相談したくても「忙しそうだから…」と遠慮してしまい、問題の発見が遅れます。
- 成長機会の喪失: 上司が部下の育成に時間を割けなくなり、チーム全体の成長がストップします。
この状況が続くと、「このチームにいても先がない」と感じた他のメンバーまで離職を考え始めるという、最悪のドミノ倒しが起こりかねません。
3. 社内での孤立と信頼の失墜 部下の離職が続けば、社内でのあなたの評判は地に落ちます。「あの人の下につくと、みんな辞めていく」「マネジメント能力がない」というレッテルを貼られ、上層部からの信頼も失墜。重要なプロジェクトから外されたり、昇進の道が閉ざされたりすることも十分に考えられます。周囲からの協力も得にくくなり、社内で孤立していくという辛い状況に追い込まれるのです。
部下の離職を軽視した場合、チームは崩壊し、自らのキャリアさえも危うくなる。これが、部下が辞め続けた後の上司を待ち受ける、残酷な末路なのです。
なぜ部下は退職理由を言わない?隠されたホンネの見抜き方
退職面談で「本当の理由」を話してくれる部下は、残念ながらごく少数です。多くの場合、「一身上の都合」や「他にやりたいことが見つかった」といった、当たり障りのない建前が語られます。上司としては、改善すべき点を知りたいのに、本音が見えずにもどかしい思いをすることでしょう。
部下が本音を言わない理由は、至ってシンプルです。
- 波風を立てたくない: どうせ辞める会社で、本当のことを言って関係性を悪化させたくない、という心理が働きます。
- 言っても無駄だと思っている: 前述の通り、「本当の原因は上司や会社にあり、それを伝えても改善されるはずがない」と諦めているケースです。
- 上司を傷つけたくない: お世話になった上司に対して、「あなたのマネジメントが原因です」とは、情の面から言いにくいと感じています。
では、この建前の裏に隠されたホンネを、どうすれば少しでも引き出すことができるのでしょうか。重要なのは、「質問」ではなく「傾聴」と「共感」の姿勢です。詰問口調で「本当の理由は何なんだ!」と迫っても、部下は心を閉ざすだけです。
以下の3つのステップを意識してみてください。
ステップ1:心理的安全性を確保する まずは、部下が安心して話せる雰囲気を作ることが最優先です。「今日ここで話した内容は、絶対に他言しないし、君の評価に影響することもないから、安心して何でも話してほしい」と伝え、安全な場であることを保証します。
ステップ2:感謝と労いの言葉を伝える 「まず、これまで会社に貢献してくれたことに心から感謝している。本当にありがとう」と、これまでの働きに対する感謝と労いを伝えます。これにより、部下の警戒心が和らぎます。
ステップ3:オープンな質問で問いかける 「もし差し支えなければ、今後の会社やチームがもっと良くなるために、何か気づいたことや、改善した方が良いと感じた点があれば、君の意見を聞かせてもらえないかな?」 このように、「あなたのため」ではなく「未来の組織のため」という視点で問いかけることで、部下は個人的な感情を抜きにして、客観的な意見として話しやすくなります。
完璧に本音を引き出すことは難しいかもしれません。しかし、最後まで相手を尊重し、真摯に耳を傾ける姿勢を見せること。それが、隠されたホンネのかけらを見つけ出し、組織の未来に繋げるための唯一の方法なのです。
-

-
【イライラ解消】業務を止めない!職場で泣くおばさんの対応策
2025/8/13
部下が辞める上司の気持ちと評価|危機を好機に変える神対処法
- 辞めてほしくない部下が出す「転職しそう」の危険な兆候5選
- 部下から退職相談を受けたら?最初の30分で信頼を得る神対応とは
- 慰留は逆効果?優秀な部下を引き止めない方が良いケースとは
- 退職が決まった部下へのスマートな接し方と円満退職のコツ
- 「辞める前にしか聞けない!部下の本音を引き出す魔法の質問5選
- もう繰り返さない!「部下が辞めないチーム」を作る上司の習慣
- まとめ|部下が辞める上司の気持ちと評価を理解し、未来へ繋げよう
辞めてほしくない部下が出す「転職しそう」の危険な兆候5選

部下の退職は、ある日突然起こるように見えて、実はその前に必ず何らかの**「兆候」**が現れています。特に、辞めてほしくない優秀な部下ほど、そのサインは些細な変化に表れるもの。これらの危険な兆候を早期に察知し、適切なアプローチをすることが、離職を防ぐための鍵となります。手遅れになる前に、以下の5つのサインを見逃さないでください。
兆候1:会議での発言が減り、表情が乏しくなる 以前は積極的に意見を出していた部下が、会議で口数が減り、どこか上の空になっている。これは、仕事やチームに対する興味・関心が薄れている非常に危険なサインです。当事者意識が低下し、「どうせ言っても無駄だ」「自分には関係ない」という諦めの境地に至っている可能性があります。
兆候2:会社や仕事に対する愚痴や不満が増える これまで前向きだった部下が、飲み会の席やちょっとした雑談で、会社の制度や仕事の進め方に対するネガティブな発言を漏らすようになった。これは、心の中に溜まった不満が、もはや抑えきれなくなっている証拠です。単なる愚痴と片付けず、その背景にある問題の根源を探る必要があります。
兆候3:急な休みや早退が増え、プライベートな予定を優先し始める 「通院」や「役所の手続き」といった理由で、平日に休みや半休を取ることが増えた。あるいは、これまで参加していた会社のイベントや飲み会を、プライベートな用事を理由に断るようになった。これらは、転職活動の面接や、社外の人との情報交換に時間を使っている可能性を疑うべきサインです。
兆光4:将来のキャリアに関する話を避けるようになる 1on1ミーティングなどで、「3年後、どうなっていたい?」といったキャリアに関する話を振っても、「特に考えていません」「まだ分かりません」と、話をはぐらかすようになった。これは、もはやこの会社でキャリアを積むことを考えていない、という意思表示かもしれません。未来の会話を避けるのは、未来の計画が会社の外にあるからなのです。
兆候5:周囲の同僚とのコミュニケーションを避けるようになる ランチや休憩時間に、いつも一緒にいた同僚と距離を置くようになったり、一人で過ごす時間が増えたりする。これは、会社への帰属意識が薄れ、人間関係をリセットしようとしているサインと考えられます。退職を決意すると、余計な情が湧かないように、無意識に周囲と距離を取ろうとする心理が働くことがあります。
これらの兆候は、あくまで可能性の一つです。しかし、複数のサインが同時に見られる場合は、注意が必要です。重要なのは、「最近、何かあった?」「疲れているように見えるけど、大丈夫?」と、非難するのではなく、気遣う姿勢で声をかけること。あなたのその一言が、部下の固く閉ざした心を開くきっかけになるかもしれません。
部下から退職相談を受けたら?最初の30分で信頼を得る神対応とは
部下から「お話があります」と、改まって声をかけられた瞬間。上司として最も冷静さが求められる場面です。この最初の30分間の対応が、部下の気持ちを動かし、場合によっては退職を思いとどまらせる可能性すら秘めています。逆に、ここで対応を間違えれば、信頼関係は完全に崩壊し、退職の意思をより固めさせてしまうでしょう。ここでは、絶対に外してはいけない「神対応」のポイントを解説します。
【神対応の5ステップ】
ステップ1:場所を変え、時間を確保する(最初の5分) まず、周囲の目がある場所で話を聞くのは絶対にNGです。「大事な話だと思うから、会議室に行こうか」と、1対1で落ち着いて話せる場所を確保します。そして、「時間は十分にあるから、焦らずに話してほしい」と伝え、部下が安心して話せる環境を整えることが最優先です。
ステップ2:徹底的に「傾聴」する(次の10分) 部下が話し始めたら、あなたはひたすら「聴く」ことに徹します。驚きや失望の表情を見せたり、「なんでだ!」と話を遮ったりするのは最悪の対応です。相槌を打ち、時折うなずきながら、部下の言葉を最後まで受け止めます。この時点でのゴールは、説得ではなく、部下の気持ちをすべて吐き出させることです。
ステップ3:感情に寄り添い、共感する(次の5分) 部下の話が一通り終わったら、まずはその決断に至った気持ちに寄り添います。「そうか、そんな風に悩んでいたんだな。話してくれてありがとう」「その決断をするのは、すごく勇気がいったと思う」と、相手の感情を肯定し、労いの言葉をかけます。部下の考えを頭ごなしに否定したり、自分の意見を押し付けたりしてはいけません。
ステップ4:事実確認と問題の切り分けを行う(次の5分) 次に、冷静に事実を確認します。「もし良かったら、その決断に至った背景をもう少し詳しく聞かせてもらえるかな?」と、退職理由の根本原因を探ります。ここで重要なのは、**「会社側で解決できる問題」か「個人側のどうしようもない問題」**かを見極めることです。業務内容や人間関係、待遇などが原因であれば、まだ改善の余地があるかもしれません。
ステップ5:次のアクションを明確にする(最後の5分) 最後に、今後の進め方を明確にします。「今日の話を一旦持ち帰って、君のために何ができるか、真剣に考えさせてほしい。来週の月曜にもう一度時間をもらえないかな?」と、具体的な次のアクションを示します。その場で無理な引き止めや安易な約束をするのではなく、「あなたのことを真剣に考えている」という姿勢を伝えることが、信頼を繋ぎとめる鍵となります。
この30分間、上司であるあなたの役割は「評価者」や「説得者」ではありません。部下のキャリアに寄り添う、一人の「伴走者」です。この姿勢を貫くことができれば、たとえ結果的に退職に至ったとしても、最後まで良好な関係を保ち、会社にとって貴重なフィードバックを得ることができるでしょう。
慰留は逆効果?優秀な部下を引き止めない方が良いケースとは

部下から退職の相談を受け、その原因が会社側にあると分かった場合、上司として慰留に動くのは当然の務めです。しかし、すべてのケースで引き止めることが正解とは限りません。 時には、無理な慰留が逆効果となり、本人のためにも会社のためにもならない結果を招くことがあります。特に、優秀な部下であればあるほど、その見極めは慎重に行うべきです。
では、どのような場合に「引き止めない」という判断が賢明なのでしょうか。
ケース1:本人の明確なキャリアチェンジの意志がある場合 「起業して自分の夢を追いかけたい」「全く異なる業界で専門性を身につけたい」といったように、本人の価値観や人生設計に深く根差した、ポジティブな理由での退職の場合です。この場合、会社が提示できる条件(給与アップや部署異動など)では、もはや本人のモチベーションを満たすことはできません。無理に引き止めれば、本人の成長の機会を奪うことになりかねません。
ケース2:会社のビジョンや文化と、本人の価値観が根本的に合わない場合 会社の理念や事業の方向性に対して、本人が根本的な疑問や不一致を感じているケースです。例えば、利益至上主義の会社の方針に、社会貢献を重視する部下が馴染めない、といった状況です。これは、どちらが良い悪いという問題ではなく、価値観のマッチングの問題です。このような部下を引き止めても、いずれ同じ理由で再び離職を考える可能性が非常に高いでしょう。
ケース3:既に信頼関係が完全に崩壊している場合 上司であるあなた自身や、会社の対応に対して、部下が既に完全な不信感を抱いてしまっている場合です。一度失われた信頼を取り戻すのは、容易なことではありません。その場で「改善する」と約束しても、「どうせ口だけで、何も変わらないだろう」と思われてしまえば、どんな慰留の言葉も響きません。
2度目の転職活動の時、上司に引き止められて一度は残ることを決めた。給与も上げてくれたし、希望の部署への異動も叶えてくれた。でも、結局1年後に辞めた。根本的な企業文化が合わなかったから、どこにいても息苦しさは変わらなかった。上司には申し訳なかったけど、あの時、自分の直感を信じて辞めておけば良かったと後悔した。 (引用元:X(旧Twitter))
このようなケースで最善の対応は、無理に引き止めることではありません。むしろ、**「君の決断を尊重する。新しいステージでの活躍を心から応援している」**と、笑顔で快く送り出してあげることです。そうすることで、本人は円満に退職でき、会社としても「アルムナイ(卒業生)」として将来的に良好な関係を築ける可能性が残ります。上司の度量の見せ所と言えるでしょう。
退職が決まった部下へのスマートな接し方と円満退職のコツ
部下の慰留が叶わず、退職が最終的に決まった。上司としては残念な気持ちでいっぱいかもしれませんが、ここからの対応こそが、あなたの管理職としての真価が問われる場面です。退職日までの期間、スマートな接し方を心がけることが、残されたチームメンバーの士気を守り、円満な退職を実現するための鍵となります。
【円満退職に向けた4つのコツ】
コツ1:態度は変えず、最後まで一人の仲間として接する 最もやってはいけないのが、退職が決まった途端に態度を冷たくしたり、無視したりすることです。「裏切り者」のような扱いをすれば、本人は居心地の悪い思いをするだけでなく、その様子を見ている他のメンバーも「この会社は辞める人間を大事にしないんだ」と会社に不信感を抱きます。これまでと変わらず、一人のチームメンバーとして尊重し、コミュニケーションを取り続けることが大切です。
コツ2:チームへの公表タイミングと内容は、本人と相談して決める 退職の事実をチームにいつ、どのように伝えるかは、非常にデリケートな問題です。必ず本人と事前にすり合わせを行いましょう。「〇月〇日の朝礼で、私から話してもいいかな?理由は、『新しいチャレンジのため』という形で伝えようと思うけど、それで問題ない?」というように、本人の意向を最大限に尊重することが、無用な憶測や混乱を防ぎます。
コツ3:引き継ぎは「丸投げ」せず、上司が責任を持って管理する 退職者本人に引き継ぎ資料の作成を丸投げするのはNGです。上司であるあなたが中心となり、「誰に」「何を」「いつまでに」引き継ぐのか、具体的な計画を立て、進捗を管理します。後任者が決まっていない場合は、一時的にチームで業務を分担できるよう采配を振るうのも、上司の重要な役割です。スムーズな引き継ぎは、残されたチームの負担を最小限に抑えるために不可欠です。
コツ4:最終日には、感謝の気持ちを言葉と形で伝える 最終出社日には、チームメンバー全員の前で、これまでの貢献に対する感謝の言葉を伝えましょう。「〇〇さんの頑張りがあったから、あのプロジェクトは成功した。本当にありがとう。新しい場所でも、〇〇さんらしく頑張ってください」といった具体的なエピソードを交えると、より気持ちが伝わります。ささやかなプレゼントや、チームでの送別会を企画するのも良いでしょう。
辞めゆく部下への態度は、残る部下たちに常に見られています。最後までプロフェッショナルとして、そして一人の人間として温かく接するあなたの姿勢は、チームのエンゲージメントを高め、組織の健全性を示す何よりの証拠となるのです。
「辞める前にしか聞けない!部下の本音を引き出す魔法の質問5選

退職が決まった部下との最終面談(エグジットインタビュー)は、組織の課題を浮き彫りにするための、またとない貴重な機会です。このタイミングだからこそ、普段は聞けない「本音」を引き出せる可能性があります。しかし、ただ「何か改善点はある?」と聞くだけでは、当たり障りのない答えしか返ってこないでしょう。ここでは、部下の本音の扉を開く「魔法の質問」を5つご紹介します。
質問1:「もし、あなたが僕の立場(上司)だったら、このチームを良くするために、まず何から始めますか?」 この質問は、相手を「当事者」に引き込む効果があります。部下は単なる批評家ではなく、問題解決の提案者という立場に立つことで、より建設的で具体的な意見を話しやすくなります。「もし自分が上司なら…」と想像することで、普段感じていた組織やマネジメントの問題点を、客観的な視点から指摘してくれるでしょう。
質問2:「この会社で働いていて、『最高の瞬間だった』と感じたのは、どんな時でしたか?それはなぜですか?」 いきなり問題点を聞くのではなく、ポジティブな質問から入るのがポイントです。部下が何にやりがいを感じ、どのような時にモチベーションが上がるのかを理解することができます。これは、会社が今後も維持・強化すべき「良い点」を把握する上で非常に重要です。成功体験を語ってもらうことで、部下の気持ちも和らぎ、その後の本音を引き出しやすくなります。
質問3:「逆に、『この時が一番辛かった』と感じたのはどんな時でしたか?どうすれば、その状況は避けられたと思いますか?」 ポジティブな話の後で、ネガティブな側面に切り込みます。単に辛かった経験を聞くだけでなく、**「どうすれば避けられたか」**という解決策までセットで聞くのがミソです。これにより、単なる愚痴で終わらせず、具体的な改善アクションに繋がるヒントを得ることができます。
質問4:「入社前に期待していたことと、実際に働いてみて感じた『ギャップ』があれば、正直に教えてもらえませんか?」 この質問は、採用活動や入社後のオンボーディング(受け入れ体制)の課題を明らかにするのに役立ちます。求人情報や面接で伝えている会社の魅力と、現場の実態との間にズレがないかを確認できます。この**「期待と現実のギャップ」**こそが、早期離職の最大の原因の一つであるため、非常に重要な質問です。
質問5:「最後に、僕自身(上司)のことで、もっとこうすれば良かった、という点があれば、今後のために遠慮なく教えてほしいです」 自分自身に対するフィードバックを、勇気を持って求める質問です。この真摯な姿勢を見せることで、部下は「この人は本気で変わろうとしているんだ」と感じ、心を開いてくれる可能性が高まります。たとえ耳の痛い指摘であったとしても、感情的にならずに感謝の気持ちを持って受け止めることが、あなたのリーダーとしての成長に繋がります。
これらの質問をする上で最も大切なのは、**「尋問」ではなく「対話」**であるという意識です。相手の言葉を否定せず、真摯に耳を傾ける。その姿勢こそが、部下からの最後の、そして最高に価値のあるプレゼント(本音)を引き出す唯一の鍵なのです。
もう繰り返さない!「部下が辞めないチーム」を作る上司の習慣
部下の離職という痛みを伴う経験を、二度と繰り返さないために。私たちは、事後対応に追われるのではなく、そもそも部下が「辞めたい」と思わないような、魅力的で働きがいのあるチームを、日頃から作っていく必要があります。ここでは、そのための上司の具体的な習慣をご紹介します。
習慣1:週に一度の「1on1ミーティング」を徹底する これは、部下の定着率を上げる上で最も効果的な習慣の一つです。目的は、業務の進捗確認ではありません。部下のためだけに時間を作り、キャリアの悩み、プライベートの状況、人間関係の課題など、何でも話せる信頼関係を築くことです。 ヤフー株式会社(現:LINEヤフー株式会社)が導入し、多くの企業に広まったこの制度は、部下の小さな変化や不満のサインを早期に察知し、問題が大きくなる前に対処することを可能にします。
習慣2:感謝と承認の言葉を「具体的」に伝える 「ありがとう」「助かるよ」といった言葉はもちろん大切ですが、さらに一歩踏み込んで、「何を」「なぜ」感謝しているのかを具体的に伝えましょう。 「先日のプレゼン資料、データ分析が的確で素晴らしかった。あのおかげで、部長も納得してくれたよ。ありがとう」 このように具体的に褒めることで、部下は「自分の仕事がちゃんと見てもらえている」「チームに貢献できている」と実感でき、承認欲求が満たされます。
習慣3:仕事を「任せる」勇気を持つ 部下の成長を促す最良の方法は、少しストレッチな(挑戦的な)仕事を任せてみることです。もちろん、失敗するリスクはあります。しかし、上司が先回りして口を出しすぎたり、マイクロマネジメントをしたりすると、部下は育ちません。**「困った時はいつでもサポートするから、まずは君のやり方でやってみて」**と、裁量権を与え、部下の自律性を信じる勇気が、部下の成長とやりがいに繋がります。
習慣4:チームの「心理的安全性」を確保する 心理的安全性とは、「このチームでは、どんな意見や質問をしても、誰も馬鹿にしたり、罰したりしない」と、メンバー全員が感じられる状態のことです。上司自身が、積極的に自分の失敗談を話したり、部下の意見を真摯に受け止めたりすることで、チーム内に「何を言っても大丈夫」という雰囲気が醸成されます。これにより、風通しの良い、活発な議論が生まれるチームになります。
習慣5:部下の「キャリア」に本気で向き合う 部下は、あなたや会社の道具ではありません。一人の人間として、それぞれのキャリアプランや人生の目標を持っています。1on1などを通じて、部下が将来どうなりたいのかを理解し、その目標達成と今の仕事を結びつける手助けをすること。これが、現代の上司に求められる最も重要な役割です。 「この上司の下にいれば、自分の市場価値を高められる」と部下が感じた時、エンゲージメントは最大化します。
これらの習慣は、一朝一夕で身につくものではありません。しかし、意識して日々実践し続けることで、あなたのチームは確実に、部下が辞めない、強く魅力的な組織へと変わっていくはずです。
まとめ|部下が辞める上司の気持ちと評価を理解し、未来へ繋げよう

この記事では、部下が辞めるという厳しい現実に直面した上司のリアルな気持ちから、それが人事評価に与える影響、そして二度と同じことを繰り返さないための具体的な対処法まで、網羅的に解説してきました。
最後に、重要なポイントを振り返りましょう。
結論として、部下の離職は、管理職の評価に明確なマイナスの影響を与えます。 しかし、その原因は上司個人だけの問題ではなく、会社の制度や本人のキャリアプランなど、様々な要因が複雑に絡み合っています。
その理由として、現代の企業は「人材の定着」を経営の最重要課題と位置づけており、管理職には短期的な業績だけでなく、「部下を育て、定着させる能力」を厳しく求めているからです。 部下の離職は、その能力が欠如している証拠と見なされてしまうのです。
具体的なアクションとして、まずは部下の退職がもたらすショックや孤独感、そして評価への不安といった「現実」を直視し、受け止めることが重要です。 その上で、退職の兆候を早期に察知し、相談を受けた際には真摯に傾聴する。そして、日頃から1on1ミーティングなどを通じて、部下が「辞めたくない」と感じるような心理的安全性の高いチームを作っていくことが求められます。
部下の離職は、確かに辛く、苦しい経験です。しかし、それはあなたのマネジメントを見つめ直し、リーダーとしてさらに大きく成長するための、**神様が与えてくれた「転機」**なのかもしれません。
この記事で得た知識を羅針盤に、目の前の危機を乗り越え、明日からあなた自身が「この人の下で働きたい」と心から思われるリーダーへと進化していくことを、切に願っています。
-

-
仕事とプライベート分ける女性|性格が違う5つの特徴と対応法
2025/12/7