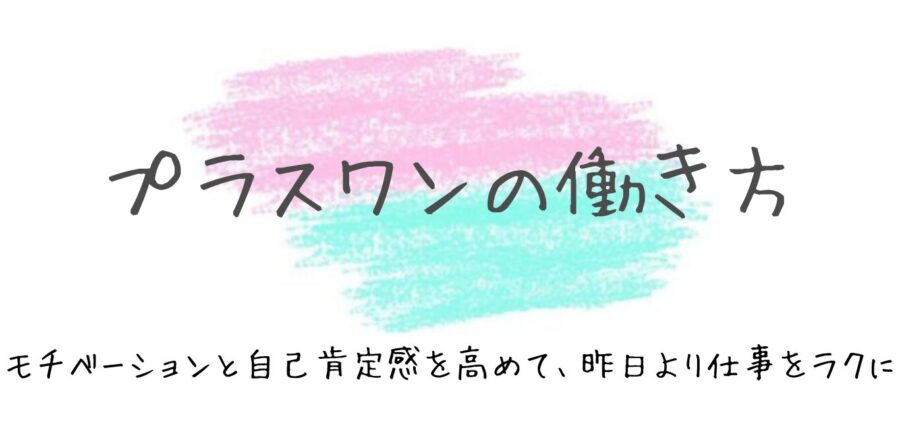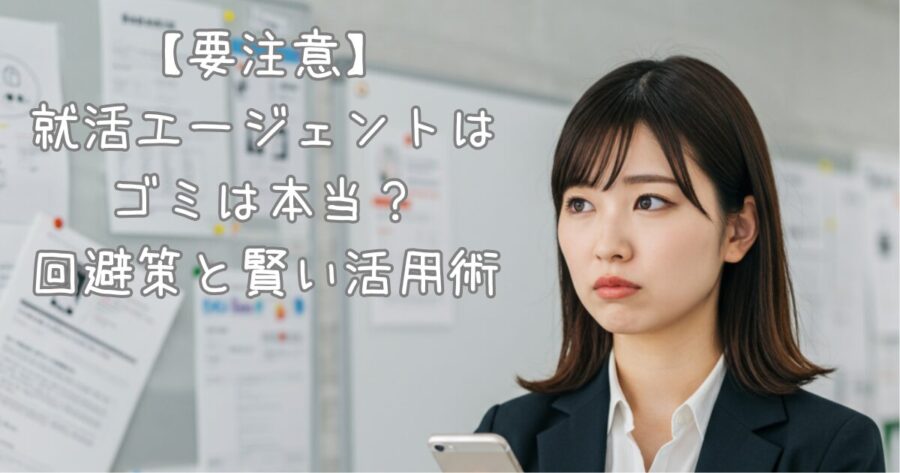「就活エージェントって本当に使って大丈夫?」「『ゴミ』とか『やばい』っていう悪い噂を聞いて、登録するのが怖い…」
就職活動という人生の大きな岐路で、専門家のサポートが受けられる就活エージェントは、とても心強い存在に見えますよね。しかし、インターネットで検索すると、そんな期待を裏切るようなネガティブな言葉が並び、不安に感じているのではないでしょうか。
ご安心ください。この記事を最後まで読めば、なぜ就活エージェントが「ゴミ」と言われてしまうのか、その根本的なカラクリが理解できます。
さらに、この記事では厚生労働省が公表しているデータや、実際のビジネスモデルに基づき、**「やばいエージェント」を見抜き、あなたの就活を成功に導くための「賢い活用術」**だけを具体的にお伝えします。
もう、悪い噂に振り回される必要はありません。正しい知識を身につけて、就活エージェントをあなたの最強の武器に変えましょう。
なぜ「就活エージェントはゴミ」と言われる?5つのやばい実態
- ビジネスモデルの闇「利益」優先でブラック求人ばかり?
- ノルマがきつい?希望無視の「ゴミ求人」を押し付けられる
- 「早く決めろ」内定承諾を迫るしつこいオワハラ手口
- 担当者がハズレで最悪!連絡がうざいし話が通じない
- 「絶対受かる」は嘘!信用できない甘い言葉で騙された話
ビジネスモデルの闇。「利益」優先でブラック求人ばかり?

「就活エージェントって、なんで無料で使えるの?」と疑問に思ったことはありませんか。その答えこそが、「就活エージェントはゴミ」と言われてしまう根本的な原因、つまりビジネスモデルの闇に繋がっています。
結論から言うと、就活エージェントは、あなたを企業に紹介し、入社が決まった時点で、その企業から「成功報酬」として年収の30%〜40%程度を受け取ることで利益を得ています。
これが何を意味するか、分かりますか?
つまり、エージェントにとってのゴールは「あなたのキャリアが成功すること」ではなく、極論すれば「あなたがどこかの企業に入社して、自社に報酬が入金されること」なのです。
もちろん、多くのエージェントは学生の未来を真剣に考えています。しかし、この「成功報酬型」という仕組みが、一部のエージェントを利益優先の行動に走らせる原因となっています。
具体的には、以下のような行動に繋がりやすいのです。
- ✅ 紹介料(報酬額)が高い企業を優先的に紹介する
- ✅ 内定が出やすい、いわゆる「誰でも受かる」企業を勧める
- ✅ 学生の希望よりも、とにかく早く内定承諾させようとする
実際に、厚生労働省の「令和5年度職業紹介事業報告書の集計結果(速報)」によると、有料職業紹介事業所の手数料収入は、全体でなんと約8,362億円にも上ります。これほど巨大な市場だからこそ、企業間の競争は激しく、利益を追求する動きが強まるのも無理はないのかもしれません。
この構造を理解しないまま、「プロが言うから大丈夫だろう」と全てを鵜呑みにしてしまうと、気づいた時には自分の希望とは全く違う、あるいは労働環境に問題のある、いわゆる**「ブラック企業」への道を歩まされていた**、なんてことにもなりかねないのです。これが、「ブラック求人ばかり紹介される」という不満の正体と言えるでしょう。
ノルマがきつい?希望無視の「ゴミ求人」を押し付けられる

「IT業界に興味があるって伝えたのに、なぜか飲食店の求人ばかり送られてくる…」
「勤務地の希望は東京だって言ったはずなのに、地方の求人を紹介された…」
こんな経験はありませんか?これは、あなたの話を聞いていないのではなく、担当者個人に課せられた「ノルマ」が原因かもしれません。
多くの人材紹介会社では、キャリアアドバイザー一人ひとりに「月の内定承諾数」や「面接設定数」といった厳しいKPI(重要業績評価指標)が設定されています。このノルマを達成しなければ、社内での評価が下がったり、給料に影響したりするため、担当者は必死です。
その結果、どうなるか。
あなたの希望や適性をじっくり分析するよりも、「とにかく内定が出そうな企業」や「手持ちの求人」を片っ端から紹介するという行動に走りがちになるのです。
まさに、質より量。担当者からすれば「数打てば当たる」かもしれませんが、学生側からすれば、それはまさに「希望を無視したゴミ求人」の押し付けに他なりません。
実際にX(旧Twitter)上でも、このような声が見られます。
就活エージェント、登録したら希望条件ガン無視のゴミ求人送りつけてくるから秒でブロックした 引用元:X(旧ツイッター)
この口コミのように、希望を丁寧にヒアリングせず、一方的に大量の求人を送りつけてくるエージェントは、あなたのキャリアを考えているのではなく、自分のノルマ達成しか見ていない可能性が非常に高いです。
また、新人の担当者などの場合、業界知識が乏しく、あなたの希望する業界の求人を十分に保有していないケースもあります。その場合、苦し紛れに全く関係のない業界の求人を紹介してくることもあるでしょう。
このような担当者に当たってしまうと、貴重な就活の時間を無駄にするだけでなく、「自分に合う仕事なんてないのかもしれない…」と、不必要に自信を失ってしまう危険性すらあるのです。
「早く決めろ」内定承諾を迫るしつこいオワハラ手口

苦労の末に、やっとの思いで勝ち取った内定。しかし、本当の恐怖はそこから始まるかもしれません。一部の悪質なエージェントは、学生が内定を獲得した途端、豹変したかのように内定承諾を迫る「オワハラ(就活終われハラスメント)」を行ってくることがあります。
- 「こんな良い企業、次はありませんよ?」
- 「他社の選考はすぐに辞退してください」
- 「今ここで決めないと、内定が取り消しになるかも…」
このような言葉で不安を煽り、冷静な判断をさせないように追い込んでくるのです。なぜ、彼らはそこまでするのでしょうか。
理由はシンプルで、あなたの内定承諾が、彼らの売上に直結するからです。
あなたが内定を承諾し、他の選考を全て辞退してくれれば、その時点でエージェントの「成果」が確定します。逆に、あなたが迷っている間に他のエージェント経由で別の企業に決めてしまったり、内定を辞退したりすると、彼らの売上はゼロになるのです。
その恐怖から、「早く決めろ」と毎日電話をかけたり、夜中にLINEを送ってきたりと、常軌を逸したしつこい連絡をしてくるケースも後を絶ちません。
X(旧Twitter)でも、生々しい体験談が投稿されています。
就活エージェントがしつこい。内定承諾を迫られてるけど、まだ就活続けたいって言ってるのに、その会社をゴリ押ししてくる。もう電話もLINEもブロックしたい。就活エージェントってこんなもんなの? 引用元:X(旧ツイッター)
このような行為は、学生の「職業選択の自由」を脅かす、非常に悪質なものです。
実際に、国民生活センターにも、「就職活動や就職セミナーに関する相談」が寄せられており、強引な勧誘や契約に関するトラブルが問題視されています。
内定は、あなたの人生を決める重要な決断です。誰かに急かされて決めるものでは決してありません。もし担当者から過度なプレッシャーを感じたら、それはあなたのためではなく、エージェント自身の利益のためだと考え、きっぱりと距離を置く勇気が必要です。
担当者がハズレで最悪!連絡がうざいし話が通じない

就活エージェントの質は、運営会社だけでなく、「誰が担当になるか」で天国と地獄ほど変わると言っても過言ではありません。残念ながら、すべての担当者が優秀で、親身になってくれるわけではないのが現実です。
いわゆる「ハズレ担当者」に当たってしまった場合、サポートを受けるどころか、ストレスを溜め込むだけの最悪な就活になりかねません。
ハズレ担当者によくある特徴は以下の通りです。
- 連絡がとにかくしつこい、うざい
- こちらの都合を考えず、昼夜問わず電話やLINEをしてくる。
- 返信を少しでも怠ると、「どうなっていますか?」と催促がすごい。
- 話が全く通じない
- こちらの希望や悩みを真剣に聞かず、マニュアル通りの返答しかしない。
- 業界や職種に関する知識が浅く、質問しても的確な答えが返ってこない。
- 高圧的、見下した態度
- 「あなたの経歴じゃ、このレベルの企業は無理」など、平気で失礼なことを言う。
- 社会人の先輩としてではなく、ただの「上から目線」で接してくる。
なぜ、このような質の低い担当者が存在するのでしょうか。
一つは、人材紹介業界が比較的参入しやすく、経験の浅い若手社員が担当者になるケースが多いためです。十分な研修を受けないまま現場に出され、学生のキャリアを導くどころか、自分の業務をこなすので精一杯という担当者も少なくありません。
X(旧Twitter)には、担当者への不満が溢れています。
就活エージェント、担当者が合わなさすぎてやばい。こっちの話全然聞いてないし、むしろ否定から入ってくる。ただでさえメンタルやられてるのに、さらに追い討ちかけてくるの何?秒で退会した。 引用元:X(旧ツイッター)
この口コミのように、担当者との相性は就活のモチベーションを大きく左右します。もし、面談の段階で「この人、ちょっと合わないな…」「なんだか信用できないな…」と感じたら、それはあなたの直感が正しい可能性が高いでしょう。
我慢して付き合い続ける必要は全くありません。担当者は変更できますし、そのエージェント自体に見切りをつけて、別のサービスを探すのが賢明な判断です。エージェント選びは、「どの会社を選ぶか」と同時に「どの担当者とパートナーを組むか」が極めて重要だと覚えておきましょう。
「絶対受かる」は嘘!信用できない甘い言葉で騙された話
「君のガクチカなら、この会社は絶対受かるよ!」
「ここは超優良企業。入れたら勝ち組だよ」
面談で担当者からこんな言葉をかけられたら、嬉しい気持ちになりますよね。しかし、その根拠のない甘い言葉は、残念ながら「嘘」である可能性が高いと警戒してください。
これらの言葉は、あなたのことを思っての言葉ではなく、あなたを特定の企業の選考に誘導するためのセールストークに過ぎません。
考えてみてください。採用を決めるのはあくまで企業側であり、一人のエージェント担当者が合否を確約できるはずがありません。それにもかかわらず「絶対」といった言葉を使うのは、学生を安心させ、行動を促すためのテクニックなのです。
このような行為は、職業安定法の第四十四条でも禁止されています。
(虚偽の広告等)
第四十四条 何人も、労働者の募集を行うに当たつては、その労働者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件について、虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を提示してはならない。
引用元:e-Gov法令検索 職業安定法
「絶対受かる」という言葉は、この「虚偽の広告等」に抵触する可能性のある、非常に無責任な発言です。
X(旧Twitter)でも、甘い言葉に裏切られた学生の声が見つかります。
就活エージェントに「君なら絶対いける!」って言われた第一志望の会社、普通に一次面接で落ちたんだが。面接対策も「自信持って!」だけだったし、期待させただけじゃん。マジで信用できない。 引用元:X(旧ツイッター)
この方のように、無責任な言葉を信じて十分な対策を怠ってしまうと、本来であれば通過できたはずの選考に落ちてしまう危険性もあります。
担当者が紹介してくれた企業や、かけてくれる言葉を一つの「参考意見」として捉え、最終的な判断は自分ですることが非常に重要です。紹介された企業については、必ず自分で公式サイトを確認したり、口コミサイトで評判を調べたりするなど、主体的な情報収集を怠らないようにしましょう。「騙された」と後悔しないために、エージェントの言葉を鵜呑みにするのは絶対にやめるべきです。
-

-
転職の証明写真はブラウスが無難?|襟あり・なし・色ガイド
2025/9/7
「就活エージェントはゴミ」を回避!賢い見分け方と活用術
- 【大前提】優良エージェントを見抜くための4つのチェック項目
- 許可番号を確認!怪しい無許可業者に登録するのはやめとけ
- 1社だけは危ない!複数のエージェントを比較してカモ回避
- 担当者が合わない…そんな時の合法的な変更依頼
- 紹介された企業は本当に大丈夫?ブラック企業か調べる裏技
- 大学のキャリアセンターとの合わせ技で効果を最大化
- まとめ|「就活エージェントはゴミ」は使い方次第で変わる
【大前提】優良エージェントを見抜くための4つのチェック項目

ここまで読んで、「やっぱり就活エージェントは怖い…」と感じたかもしれません。しかし、全ての就活エージェントが「ゴミ」なのではなく、中には本当に親身になってあなたのキャリアをサポートしてくれる優良なエージェントも数多く存在します。
問題は、その「優良エージェント」をどうやって見抜くか、です。
闇雲に登録する前に、最低限、以下の4つの項目を必ずチェックする習慣をつけましょう。これだけで、悪質な業者に引っかかるリスクを劇的に減らすことができます。
✅ 1. 厚生労働省の許可番号があるか?
これは最も重要なチェック項目です。日本で人材紹介業を営むには、必ず厚生労働大臣の許可が必要となります。厚生労働省職業安定局の人材サービス総合サイトの会社概要ページなどに「有料職業紹介事業許可番号 〇〇-ユ-〇〇〇〇〇〇」といった記載があるかを確認しましょう。この番号がない業者は、法律を守っていない「違法業者」であり、絶対に利用してはいけません。
✅ 2. プライバシーマークを取得しているか?
就活エージェントには、履歴書や職務経歴書など、膨大な個人情報を提供することになります。プライバシーマーク(Pマーク)は、個人情報を適切に管理している事業者であることを示す第三者認証です。このマークがあるかどうかは、あなたの個人情報を大切に扱ってくれるかどうかの、一つの信頼の証となります。
✅ 3. 得意な業界・職種が明確か?
「どんな業界でもお任せください!」というエージェントよりも、「IT業界特化」「メーカー専門」のように、特定の分野に強みを持つエージェントの方が、専門的な知識や、質の高い非公開求人を保有している可能性が高いです。あなたの希望する業界が決まっているなら、その分野に特化したエージェントを選ぶのが成功への近道となります。
✅ 4. 悪い口コミだけでなく、良い口コミも豊富か?
ネット上の口コミを調べる際は、悪い評判だけに目を向けるのではなく、良い評判にも注目しましょう。どんなサービスにも批判的な意見はつきものですが、「担当者が親身だった」「自分に合う企業を紹介してくれた」といったポジティブな声が数多く見つかるエージェントは、それだけ多くの就活生を満足させてきた実績があると言えます。X(旧Twitter)やみん就、ONE CAREERなどの就活サイトで、リアルな声を探してみるのがおすすめです。
これらの4つの項目をクリアしているエージェントは、比較的安心して利用できる可能性が高いと言えるでしょう。面倒くさがらずに、登録前のひと手間で、あなたの就活を守りましょう。
許可番号を確認!怪しい無許可業者に登録するのはやめとけ
先ほどのチェック項目でも触れましたが、数あるポイントの中でも絶対に外してはいけないのが「許可番号」の確認です。これを怠ることは、身分証明書も持たない怪しい人に、自分の個人情報を全て渡すのと同じくらい危険な行為だと認識してください。
なぜ、そこまで重要なのでしょうか。
それは、厚生労働省の許可を得ずに職業紹介を行う「無許可業者」が、残念ながら存在するからです。こうした違法業者は、法律による規制を受けないため、以下のような深刻なトラブルを引き起こす可能性があります。
- 🚨 個人情報の不正利用・漏洩あなたの履歴書情報が、知らない間に他の企業に売られてしまう危険性があります。
- 🚨 虚偽の求人情報聞いていた条件と全く違う、劣悪な労働環境の職場を紹介される可能性があります。
- 🚨 トラブル時の責任逃れ問題が発生しても、「うちは関係ない」とサポートを放棄され、泣き寝入りするしかなくなる恐れがあります。
「でも、どうやって確認すればいいの?」
確認方法は、実はとても簡単です。
ステップ1:エージェントの公式サイトをチェック
多くの場合、公式サイトの「会社概要」やフッター(一番下の部分)に、「有料職業紹介事業許可番号 〇〇-ユ-〇〇〇〇〇〇」という記載があります。
ステップ2:厚生労働省のサイトで検索
もし公式サイトで見つからない場合や、念のために確認したい場合は、厚生労働省が運営する「人材サービス総合サイト」で検索できます。このサイトの「職業紹介事業者検索」で会社名を入力すれば、許可を受けている正規の事業者かどうかを誰でも確認することが可能です。
実際に、許可なく職業紹介を行ったとして、事業停止命令などの行政処分を受ける企業も存在します。例えば、過去には役員の欠格事由を理由に、職業紹介事業の許可が取り消された事例も厚生労働省から発表されています。
たった数分の確認作業を惜しんだせいで、取り返しのつかないトラブルに巻き込まれることだけは絶対に避けるべきです。あなたの輝かしいキャリアの第一歩を、怪しい無許可業者に汚させるわけにはいきません。登録ボタンを押す前に、必ず「許可番号」を確認する。これを鉄則にしてください。
1社だけは危ない!複数のエージェントを比較してカモ回避
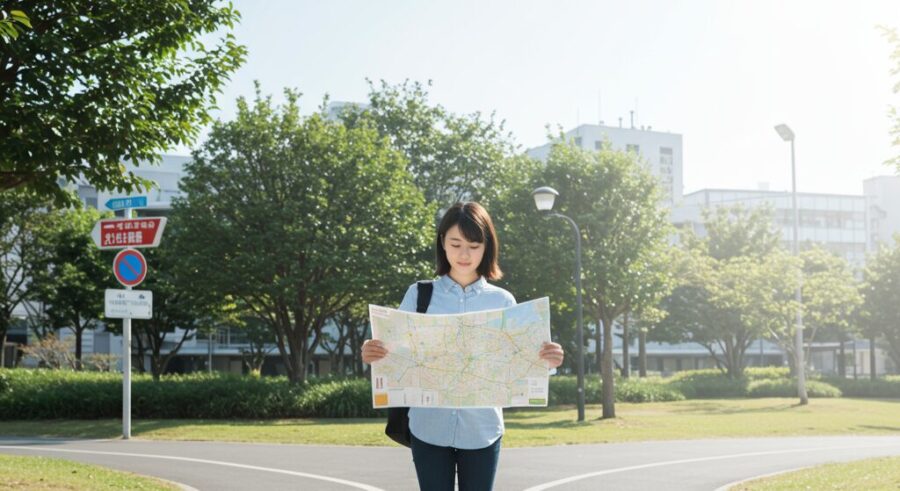
「とりあえず有名なエージェントに1社だけ登録しておけば安心だろう」
もしあなたがそう考えているなら、その考えは非常に危険です。なぜなら、1社だけの利用は、まさにエージェントにとって「カモ」になりやすい状況を自ら作り出していることに他ならないからです。
就活を成功に導くための鉄則、それは「就活エージェントは最低でも2〜3社、複数登録して比較検討する」ことです。
面倒に感じるかもしれませんが、複数登録にはそれを補って余りある、以下のような絶大なメリットがあります。
メリット1:担当者の「当たり外れ」リスクを分散できる
前の章でも述べた通り、担当者の質は様々です。もし、最初に登録した1社の担当者が「ハズレ」だった場合、あなたは「就活エージェントなんてこんなものか…」と諦めてしまうかもしれません。しかし、複数登録していれば、「A社の担当者は合わないけど、B社の担当者は親身になってくれる」というように、自分に合った最高のパートナーを見つけ出すことが可能になります。
メリット2:客観的な視点(セカンドオピニオン)が持てる
1社だけの利用だと、その担当者の意見が全てになってしまい、視野が狭くなりがちです。例えば、A社から「君には営業職しかない」と言われても、B社からは「あなたの強みは企画職で活かせる」と提案されるかもしれません。複数のプロの意見を聞くことで、自分の可能性を多角的に知ることができ、より納得感のある企業選びができます。
メリット3:「独占求人」の取りこぼしを防げる
多くのエージェントは、その会社でしか紹介していない「非公開求人」や「独占求人」を持っています。あなたが本当に入りたいと思えるような優良企業が、たまたま登録していないエージェントの独占求人だった、という機会損失を防ぐためにも、複数登録は非常に有効なのです。
X(旧Twitter)でも、複数利用の重要性を指摘する声が多く見られます。
就活エージェントは絶対複数登録した方がいい。1社だけだと担当者の言うこと鵜呑みにしちゃうし、求人も偏る。私は3社登録して、一番親身で的確なアドバイスくれるとこに絞って使ってる。結果、自分じゃ見つけられなかった優良企業に出会えた。 引用元:X(旧ツイッター)
このように、複数のサービスを「比較検討」することで、初めて自分にとって最適なサポートが見つかります。1社に依存するのではなく、あなたがエージェントを「選ぶ」という強い意志を持つこと。それが、悪質なエージェントの言いなりにならず、「カモ」にされるのを防ぐ最も賢い方法なのです。
「選考を受けた企業」からフィードバックがもらえる&面接やES対策に強い就活エージェントはこちら→大手企業の現役面接官が運営する就活エージェント【ユメキャリAgent】
担当者が合わない…そんな時の合法的な変更依頼
「この担当者、どうも合わないな…」「なんだか信用できない…」
面談を重ねるうちに、担当者に対してそんな不満や違和感を抱くことは、決して珍しいことではありません。そんな時、多くの就活生が「変更をお願いしたら気まずいかな」「我慢するしかないのか…」と悩んでしまいますが、その必要は全くありません。
結論から言うと、担当者の変更を依頼することは、あなたの正当な権利です。
考えてみてください。あなたは、自分の人生を左右するかもしれない重要な相談を、信頼できない相手に続けたいと思うでしょうか。合わない担当者と無理に就活を続けることは、時間の無駄であるだけでなく、精神的にも大きなストレスとなります。
担当者変更をスムーズに行うための、具体的なステップと伝え方のポイントをご紹介します。
ステップ1:変更依頼の連絡手段を決める
担当者に直接言いにくい場合は、そのエージェントの公式サイトにある「お問い合わせフォーム」や、総合受付の電話番号から連絡するのがおすすめです。これなら、担当者本人を通さずに、事務的に変更を依頼できます。
ステップ2:変更理由は正直かつ簡潔に伝える
変更理由を伝える際は、個人攻撃にならないように注意しつつも、正直に理由を伝えることが大切です。角が立たない伝え方の例文をいくつかご紹介します。
- (当たり障りのない理由)「お世話になっております。〇〇大学の〇〇です。大変恐縮なのですが、他の担当者の方のご意見もお伺いして、より視野を広げたいと考えております。担当者の変更を検討いただくことは可能でしょうか。」
- (より具体的な理由)「〇〇様には大変お世話になっておりますが、私が希望するIT業界について、より専門的な知見をお持ちの方にご担当いただくことは可能でしょうか。」
- (相性の問題を伝える場合)「大変申し訳ないのですが、今後のキャリアについてのご相談の方向性に少し相違を感じております。つきましては、担当者の変更をお願いできますでしょうか。」
重要なポイント
💡 感情的にならないこと:「あの担当者は最悪だ!」といった感情的な表現は避けましょう。
💡 感謝の言葉を添えること:「これまでサポートいただいたことには感謝しております」といった一言を添えると、よりスムーズに話が進みます。
もし、会社側が担当者の変更に応じてくれなかったり、不誠実な対応をされたりした場合は、そのエージェント自体に見切りをつけ、すぐに退会して別のエージェントを利用しましょう。そんな会社は、そもそも社員教育ができていない、信頼できない会社である可能性が高いです。
あなたの就活の主役は、あなた自身です。担当者はあくまでサポート役。あなたが最高のサポートを受けられる環境を自ら作るために、遠慮なく「担当者変更」というカードを使いましょう。
紹介された企業は本当に大丈夫?ブラック企業か調べる裏技

「この企業、すごく評判が良いんですよ!」
「離職率も低く、働きやすい環境です」
エージェントからこのように勧められると、「プロが言うなら間違いないだろう」と信じてしまいそうになりますよね。しかし、その言葉を鵜呑みにするのは非常に危険です。なぜなら、エージェントは企業の良い側面をアピールするプロではあっても、全てのネガティブな情報を開示してくれるとは限らないからです。
自分の未来を守るためには、紹介された企業の実態を**あなた自身の手で調べる「裏付け調査」**が不可欠です。
ここでは、誰でも簡単にできる、ブラック企業かどうかを調べるための具体的な「裏技」を2つご紹介します。
裏技①:国のデータベースで「行政処分歴」を確認する
もし、その企業が過去に労働基準法違反などで国から行政指導を受けていたとしたら…?そんな危険な兆候を察知できるのが、厚生労働省の「労働基準関係法令違反に係る公表事案」というサイトです。ここで企業名を検索し、もしヒットした場合は、労働関連の法令を遵守する意識が低い企業である可能性が高く、注意が必要です。
裏技②:「退職」のプロの情報を参考にする
これは少し意外な方法かもしれませんが、非常に有効です。世の中には「退職代行サービス」という、労働者の退職手続きを代行するサービスがあります。つまり、「退職代行サービス」から「多くの人が辞めたがっている企業」の傾向を知ることができるのです。これは、入社を避けるべき企業を見極める上で、非常に強力な判断材料となるでしょう。
MOMURI+(モームリプラス)では、
『退職情報開示サービス
』を実施しています。
このサービスは、あなたが応募しようとしている企業について、過去にモームリの退職代行サービスを利用して退職した人がいるかどうか、その実績データを有料で開示してくれます。
- もし「利用実績あり」と出たら…必ずしもブラック企業だと断定はできませんが、少なくとも「退職時にトラブルを抱えた人が過去にいた」という事実がわかります。面接の際に、社員の定着率や退職理由について、少し踏み込んだ質問をしてみるなどの対策が取れるでしょう。
- もし「利用実績なし」と出たら…それは、社員が円満に退職できている健全な企業である可能性が高い、という一つの安心材料になります。
これらの「裏技」を駆使して、エージェントからの情報と、あなた自身で集めた情報を照らし合わせることで、初めてその企業の実態が見えてきます。自分の目で確かめる一手間が、入社後の「こんなはずじゃなかった…」という後悔を防ぐ、何よりの保険になるのです。
▼後悔しない就活のために。応募企業の「退職代行の利用状況の確認」はこちらから▼

大学のキャリアセンターとの合わせ技で効果を最大化
就活の相談先として、就活エージェントと並んで大きな存在なのが、あなたが通う「大学のキャリアセンター(就職課)」です。
「エージェントを使っているから、キャリアセンターは必要ないかな?」
そう考えるのは、非常にもったいないです!
実は、就活エージェントと大学のキャリアセンターは、それぞれに得意なこと・不得意なことがあります。両方のメリットを理解し、**賢く使い分ける「合わせ技」**こそが、就活の成功確率を最大化する最強の戦略なのです。
まずは、それぞれの特徴を比較してみましょう。
| 就活エージェント | 大学のキャリアセンター | |
| 求人の数 | 〇(非常に多い・全国規模) | △(大学に来る求人が中心) |
| 求人の質 | △(玉石混交) | ◎(大学がフィルタリング済み) |
| サポート | ◎(ES添削・面接対策が手厚い) | 〇(担当者による) |
| 情報 | 〇(幅広い業界情報) | ◎(OB/OG情報・学内推薦) |
| 信頼性 | △(利益優先の可能性) | ◎(完全に学生の味方) |
| 利用しやすさ | 〇(オンライン・夜間対応も) | △(学内・日中のみ) |
この表から分かるように、それぞれに一長一短があります。
そこで、以下のような「合わせ技」を実践するのがおすすめです。
活用戦略①:情報収集は「エージェント」、裏付けは「キャリアセンター」
エージェントから紹介された求人や、勧められた業界について、「この企業、大学に求人は来ていますか?」「OB/OGで活躍している先輩はいらっしゃいますか?」とキャリアセンターで相談してみましょう。もし大学に求人が来ていなかったり、OB/OGからの評判が悪かったりすれば、少し立ち止まって考えるきっかけになります。
活用戦略②:選考対策は両方で受ける
ES(エントリーシート)や面接の対策は、できるだけ多くの大人に見てもらうのが効果的です。エージェントの担当者(企業の視点)と、キャリアセンターの職員(教育者の視点)という、異なる角度からフィードバックをもらうことで、あなたの自己PRはさらに磨かれます。
活用戦略③:「学内推薦」はキャリアセンターで確認
企業によっては、大学ごとに推薦枠を設けている「学内推薦」というルートがあります。これは一般応募よりも有利に進むことが多い、非常に貴重なチャンスです。こうした情報は、キャリアセンターでしか得られません。
就活エージェントは「就活市場全体を広く見るための武器」、大学のキャリアセンターは「自分の大学の強みを最大限に活かすための盾」と考えると分かりやすいでしょう。
どちらか一方に偏るのではなく、両方を戦略的に使いこなす。それこそが、情報に惑わされず、自分にとって最高の選択をするための賢い就活生の姿なのです。
まとめ|「就活エージェントはゴミ」は使い方次第で変わる

今回は、「就活エージェントはゴミ」という噂がなぜ流れるのか、その真相と、悪質なエージェントを回避して就活を成功させるための具体的な方法について徹底的に解説してきました。
最後に、この記事の重要なポイントをまとめます。
- ✅ 「ゴミ」と言われる背景には、企業から報酬を得る「成功報酬型」というビジネスモデルがあり、利益優先の行動に繋がりやすい。
- ✅ 担当者のノルマや質のばらつきが、「希望無視の求人」や「オワハラ」といったトラブルの原因になっている。
- ✅ 回避策の第一歩は、国の許可を得た事業者かを示す「許可番号」を必ず確認すること。
- ✅ 1社だけの利用は危険。必ず複数社に登録し、担当者や求人を「比較検討」する視点を持つことが重要。
- ✅ 担当者が合わない場合は、遠慮なく変更を依頼する権利がある。
- ✅ エージェントの情報を鵜呑みにせず、口コミサイトや大学のキャリアセンターを活用して「裏付け調査」をすることが不可欠。
結論として、就活エージェントは、決して全て「ゴミ」ではありません。
しかし、その仕組みを理解せず、ただ受け身で利用してしまうと、不利益を被る可能性があるのもまた事実です。
大切なのは、エージェントを「使う」のではなく、「主体的に使いこなす」という姿勢です。
あなたがこの記事で得た知識を武器に、冷静な目でエージェントを選び、彼らを自分の夢を叶えるためのパートナーとして活用していくこと。それができれば、就活エージェントはあなたの就職活動において、これ以上ないほど心強い味方になってくれるはずです。
あなたの就職活動が、後悔のない素晴らしいものになることを心から応援しています。
-

-
仕事が忙しいと恋愛感情はなくなる?別れを回避する復活の秘訣
2025/7/26