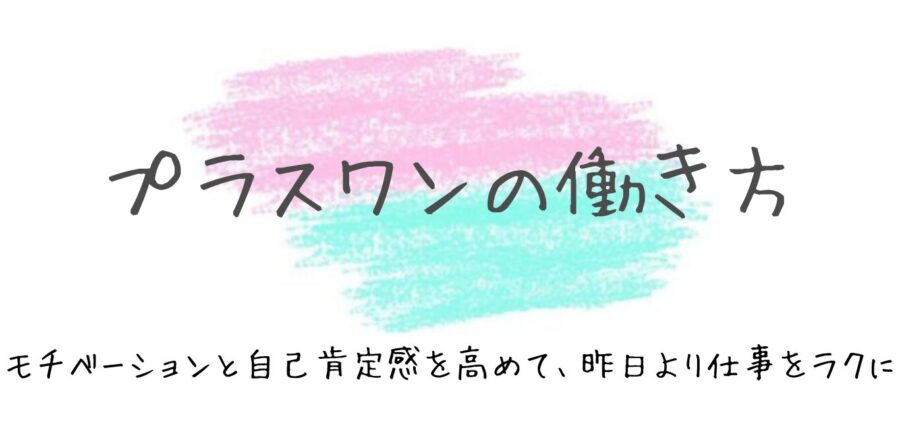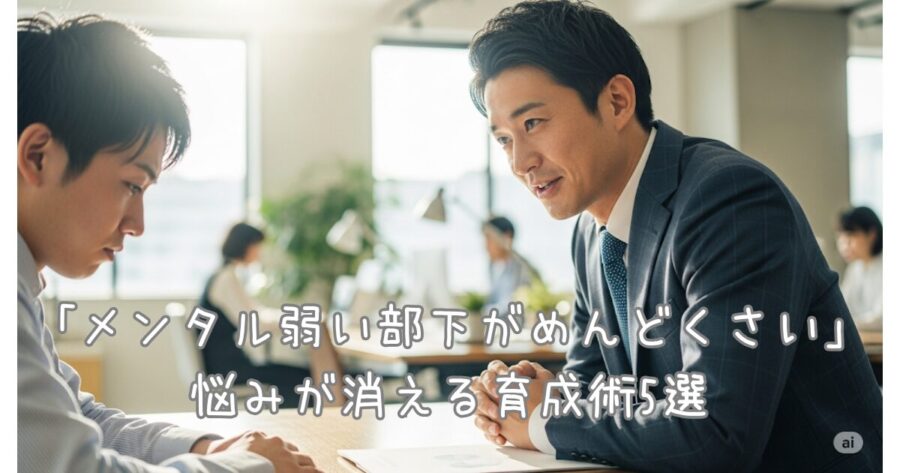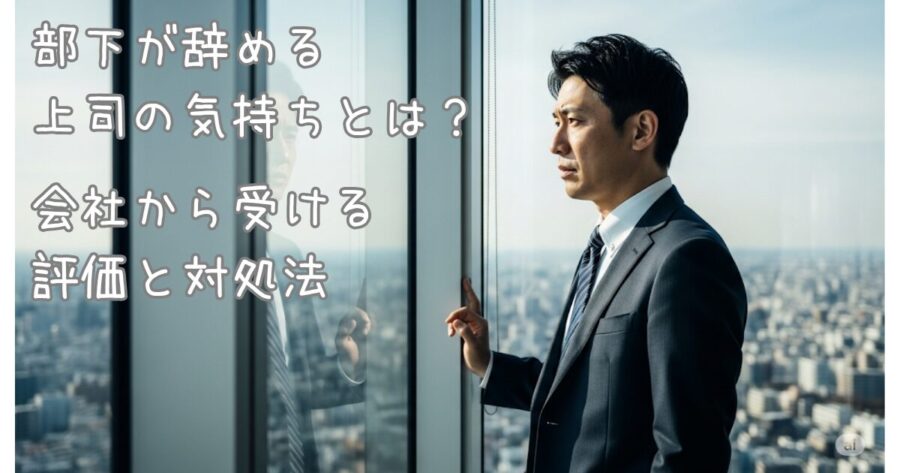「また休むのか…」「どうしてこんな些細なことで落ち込むんだ?」
メンタルが弱い部下との関わり方に、正直「めんどくさい」と感じていませんか?
その気持ち、非常によく分かります。上司だって一人の人間です。自分の業務に追われる中で、部下のケアまで手が回らないと感じるのは当然のことかもしれません。
しかし、そのネガティブな感情は、正しい知識と育成術で「頼もしい戦力」へと変えることができます。
実は、部下のメンタルの弱さの背景には、世代間の価値観の違いや、職場環境の問題が隠れているケースが少なくありません。
この記事では、厚生労働省のデータや、先進企業の具体的な取り組みを基に、あなたが抱える「めんどくさい」という悩みの根本原因を解き明かします。そして、明日からすぐに実践できる具体的な育成術を5つ、分かりやすく解説していきます。
この記事を最後まで読めば、部下への見方が変わり、チーム全体を成功に導くための具体的な道筋が見えてくるはずです。あなたの悩みを、部下とチームの成長のきっかけに変えていきましょう。
なぜ?「メンタル弱い部下めんどくさい」と感じる本当の理由
- 正直な本音…『めんどくさい』と感じるのは普通のことです
- 特徴はコレ!メンタルが弱い部下に共通する5つのサイン
- Z世代の価値観とは?『わがまま』に見える理由と本質
- それは「甘え」?それとも「不調」?危険なサインの見極め方
- 泣く新入社員は危険信号?放置が招く職場トラブルとは
- 実は部下でなく環境の問題?心理的安全性の低い職場の特徴
- それ、パワハラかも?上司が知らないと危険な法的リスク
正直な本音…『めんどくさい』と感じるのは普通のことです

結論から言うと、メンタルの弱い部下に対して「めんどくさい」と感じてしまうのは、上司としてごく自然な感情です。決して、あなたが冷たい人間だとか、上司失格だというわけではありません。なぜなら、上司にはチーム全体の成果を上げるという大きな責任があり、そのプレッシャーの中で、部下の一人ひとりの感情の機微にまで完璧に対応するのは、非常に困難なことだからです。特に、予期せぬ欠勤や、業務の遅延、頻繁な相談など、計画通りに進まない事態が続けば、苛立ちや徒労感を覚えてしまうのも無理はありません。
実際に、管理職の多くが同様の悩みを抱えています。
部下のメンタルヘルス不調に対応した経験のある管理職のうち、約5割は「精神的な負担が大きかった」、約4割は「業務上の負担が大きかった」と回答しています。さらに、対応における課題として「他のメンバーの業務量増加(35.2%)」が最も多く、次いで「業務の調整負担(26.2%)」が続くなど、管理職が精神的・業務的の両面で大きな負荷を背負っている実態が明らかになっています。
引用元:パーソル総合研究所「若手従業員のメンタルヘルス不調についての定量調査」
このように、多くの管理職が部下のメンタルヘルス対応に苦慮しているのが現実です。自分の感情を責める前に、まずは「自分だけじゃないんだ」と認識することが大切です。その上で、なぜ「めんどくさい」と感じてしまうのか、その感情の源泉を冷静に分析してみましょう。
✅ 自分の期待通りに動いてくれないことへの不満 ✅ コミュニケーションにかかる時間的・精神的コスト ✅ チーム全体のパフォーマンス低下への懸念 ✅ どう接すれば良いか分からないという戸惑い
これらの感情は、責任感が強い上司ほど抱えやすいものです。大切なのは、その感情に蓋をせず、「自分は今、こう感じているんだな」と客観的に受け止めること。そして、その感情をバネにして、部下との関わり方を見直すきっかけと捉えることです。この記事では、そのための具体的な方法を解説していきますので、まずは自分自身の感情を肯定することから始めてみてください。
特徴はコレ!メンタルが弱い部下に共通する5つのサイン
「メンタルが弱い」と一括りにしてしまいがちですが、その行動の裏には、いくつかの共通した心理的な特徴(サイン)が隠されています。これらのサインを早期に察知し、理解することが、適切な対応への第一歩となります。ここでは、特に見られがちな5つの特徴を解説します。これらのサインは、単なる「性格」の問題ではなく、本人が抱えるストレスや不安の表れであると捉えることが重要です。
- 自己評価が極端に低い 「どうせ私なんて」「私には無理です」といったネガティブな発言が口癖になっていませんか?これは、自己肯定感の低さの典型的なサインです。自分の能力や価値を過小評価してしまうため、新しい仕事や少し難易度の高い課題に対して、挑戦する前から諦めてしまう傾向があります。成功体験が少ない、あるいは過去の失敗経験がトラウマになっているケースも考えられます。
- 他人の評価を過剰に気にする 上司や同僚からどう見られているかを常に気にして、ビクビクしている様子はありませんか。他人の評価が自分の価値を決めるという「他人軸」で生きているため、少しでも否定的なフィードバックを受けると、自分の全人格を否定されたかのように感じてしまいます。SNSの「いいね!」の数を気にする感覚に近いかもしれません。
- 完璧主義で失敗を極度に恐れる 「100点でなければ0点と同じ」という思考に陥りがちなのも特徴です。高い理想を掲げる一方で、それを達成できなかった時のショックが大きいため、失敗を恐れて行動できなくなってしまいます。資料作成に時間をかけすぎる、間違いを指摘されるとひどく落ち込む、といった行動が見られたら、このタイプかもしれません。
- ネガティブな思考の罠に陥りやすい 物事の良い面よりも、悪い面にばかり目がいってしまう傾向があります。例えば、9割うまくいっていても、残りの1割のミスに固執し、「すべてがダメだった」と結論づけてしまいます。このような思考の癖は、本人の意欲を削ぎ、前向きな行動を妨げる大きな原因となります。
- ストレスが体調不良として現れやすい 精神的なストレスが、頭痛、腹痛、めまい、不眠といった身体的な症状として現れることも少なくありません。特に、月曜日の朝や重要な会議の前などに体調を崩すことが多い場合、それは心からのSOSサインである可能性が高いです。厚生労働省が提供するストレスチェック制度も、このような心身の不調に気づくための有効なツールとされています。
これらのサインは、一つだけでなく複数当てはまることが多いです。部下の言動を注意深く観察し、「もしかしたら、今、このサインが出ているのかも?」と気づくことができれば、感情的に「めんどくさい」と突き放すのではなく、具体的なサポートを考えるきっかけになるはずです。
Z世代の価値観とは?『わがまま』に見える理由と本質

「最近の若者は打たれ弱い」「プライベートを優先してわがままだ」と感じることはありませんか?特に1990年代後半から2010年代序盤に生まれた「Z世代」と呼ばれる部下に対して、そうした印象を抱く上司は少なくないようです。しかし、彼らの行動を単に「わがまま」や「根性なし」と切り捨てるのは早計です。その背景には、私たち世代とは異なる、彼ら独自の価値観が存在します。その本質を理解することが、円滑なコミュニケーションの鍵となります。
Z世代の価値観を形成した大きな要因は、生まれた時からインターネットやSNSが当たり前に存在する**「デジタルネイティブ」**であることです。これにより、彼らには以下のような特徴が見られます。
- 多様性の受容と個の尊重 SNSを通じて、世界中の多様な価値観に触れながら育ってきました。そのため、「みんな違って当たり前」という感覚が強く、個人の意見や生き方が尊重されることを重視します。上司からの画一的な指示や「昔はこうだった」という経験談には、強い抵抗を感じることがあります。
- タイムパフォーマンス(タイパ)意識 膨大な情報の中から、自分に必要なものを効率的に取捨選択することに長けています。そのため、仕事においても無駄を嫌い、目的や意味が不明確な作業には疑問を抱きやすい傾向があります。これが、時に「楽をしようとしている」と見えてしまう原因かもしれません。
- 仕事とプライベートの明確な分離 ワークライフバランスではなく、**ワークライフインテグレーション(仕事と生活の統合)**を重視する傾向があります。仕事はあくまで人生の一部であり、プライベートな時間や自己実現を犠牲にしてまで会社に尽くす、という考え方は希薄です。定時で帰ることや有給休暇の取得は、彼らにとって当然の権利なのです。
- オープンなコミュニケーションへの期待 SNSでのフラットなコミュニケーションに慣れているため、職場の人間関係においても、風通しの良さや透明性を求めます。上司に対しても、自分の意見を率直に伝えることがありますが、それは反抗心からではなく、より良い成果を出すための提案であるケースが多いのです。
X(旧Twitter)上でも、Z世代の仕事観に関する様々な意見が見られます。
会社に人生捧げるつもりないし、プライベートの時間削ってまで仕事したくない。給料分の働きはするけど、それ以上は求めないでほしいのが本音。これってZ世代のわがままなのかな? 引用元:X(旧Twitter)
このような声は、まさに彼らの価値観を象徴しています。上司の世代が「会社への忠誠心」や「滅私奉公」を美徳としてきたのとは対照的です。このギャップを理解せず、一方的に「わがまま」と決めつけてしまうと、部下のモチベーションを著しく低下させ、最悪の場合、早期離職につながってしまいます。彼らの行動の裏にある**「なぜそう考えるのか?」という背景**に目を向け、対話を試みることが、新時代のマネジメントには不可欠と言えるでしょう。
それは「甘え」?それとも「不調」?危険なサインの見極め方
部下のパフォーマンスが低下したり、休みがちになったりした時、「それは本人の甘えではないか?」と感じてしまうことがあるかもしれません。確かに、単なる意欲の低下であるケースもゼロではありません。しかし、それを安易に「甘え」と決めつけ、精神論で叱咤激励するのは非常に危険です。なぜなら、その背後には**うつ病などの精神的な不調(メンタルヘルス不調)**が隠れている可能性があるからです。ここでは、「甘え」と「不調」を見極めるための重要なポイントを解説します。
まず大前提として、上司が医学的な診断を下すことはできません。最終的な判断は医師に委ねるべきですが、職場として危険なサインに気づき、専門家へつなぐ役割を担うことは可能です。以下の表は、一般的な「甘え」と、注意すべき「不調のサイン」の違いをまとめたものです。
| 観点 | 甘え(一時的な意欲低下) | 不調のサイン(受診を検討すべき状態) |
|---|---|---|
| 期間 | 一時的(数日〜1週間程度)で、状況によって変動する。 | 2週間以上、ほぼ毎日、一日中続く。 |
| 状況 | 嫌な仕事の時だけ意欲が下がるなど、状況に左右される。 | 仕事だけでなく、趣味など好きなことにも興味を失う。 |
| 身体症状 | 特に見られないことが多い。 | 不眠、食欲不振、頭痛、倦怠感など、明らかな身体症状を伴う。 |
| 思考 | 「やりたくない」「面倒」といった思考。 | 「自分は価値がない」「消えてしまいたい」といった強い自己否定や希死念慮。 |
| 周囲への影響 | 特定の人や業務に対してのみ態度が変わる。 | 周囲との交流を避けるようになり、孤立していく。 |
最も重要な判断基準は**「変化」と「期間」**です。以前は活発だった部下が、明らかに別人かのように元気がなくなり、その状態が2週間以上続いている場合は、専門家への相談を促すことを真剣に検討すべきです。
厚生労働省のポータルサイト「こころの耳」では、事業者が実施すべき「4つのケア」の一つとして、「ラインによるケア」の重要性が指摘されています。これは、管理監督者が部下の異変にいち早く気づき、相談対応や職場環境の改善を行うことを指します。
「いつもと違う」部下の様子に気づくためには、日頃から部下の状況を把握しておくことが大切です。遅刻、早退、欠勤が増える、仕事の能率が落ちる、ミスが増える、表情が暗い、元気がない、口数が減る、逆に多弁になる、など、様々な変化がサインとなります。
引用元:厚生労働省「こころの耳」
部下の様子を「甘えだ」と主観で判断するのではなく、「いつもと違う」という客観的な事実に基づいて観察することが重要です。そして、少しでも懸念があれば、「最近、よく眠れてる?」「何か困っていることはない?」と、決めつけずに尋ねる姿勢が、部下を深刻な事態から救う第一歩となるのです。
泣く新入社員は危険信号?放置が招く職場トラブルとは

業務上の指導をしている最中に、新入社員や若手の部下が突然泣き出してしまい、戸惑った経験はありませんか?「こんなことで泣くなんて…」と呆れてしまったり、「めんどくさい」と感じたりするかもしれません。しかし、部下が流す涙は、本人からのSOSサインであり、職場環境に潜む問題点を知らせる危険信号である可能性が高いのです。これを個人の弱さの問題として片付け、放置してしまうと、後々深刻な職場トラブルに発展しかねません。
部下が泣いてしまう主な理由としては、以下のようなものが考えられます。
- キャパシティオーバー: 自分の能力を超える業務量やプレッシャーに押しつぶされそうになっている。
- 強い不安や恐怖: 上司の厳しい口調や高圧的な態度に、威圧感や恐怖を感じている。
- 理不尽さへの悔しさ: 自分の意見を聞いてもらえない、正当な評価をされていないと感じ、悔しさや無力感を抱いている。
- 共感性の高さ: 他人の感情に影響を受けやすく、職場のギスギスした雰囲気に耐えられなくなっている。
これらの感情が涙として溢れ出た時、上司が取るべきでない対応は、「泣けば済むと思うな!」「甘えるな!」といった感情的な叱責です。これは、部下の心をさらに深く傷つけ、信頼関係を完全に破壊してしまいます。
では、なぜ放置が危険なのでしょうか。それは、以下のようなリスクを招くからです。
- メンタルヘルス不調の悪化 泣くという行為は、精神的にかなり追い詰められている証拠です。ここで適切なフォローがなければ、うつ病などの精神疾患を発症するリスクが高まります。
- ハラスメント問題への発展 上司の指導が、本人の意図とは関係なく、部下にとっては「パワーハラスメント」と受け取られている可能性があります。涙を無視し、厳しい指導を続ければ、ハラスメントとして訴えられるリスクも否定できません。
- チームの士気低下と生産性悪化 一人の社員が泣いている状況は、周囲の社員にも「この職場は心理的に安全ではない」というメッセージを与えてしまいます。結果として、チーム全体の雰囲気が悪化し、コミュニケーションが停滞。生産性の低下につながります。
- 離職率の増加 「この職場では安心して働けない」と感じた社員は、早期離職を選択します。特に優秀な人材ほど、より良い環境を求めて去っていく傾向があります。
実際に、部下の涙をきっかけに自身の指導方法を見直したという管理職の声もあります。
新人に業務のミスを指摘したら、ポロポロ泣き出してしまって本当に焦った。最初は「え、なんで?」って思ったけど、よくよく話を聞いたら、他の先輩からも色々言われてパンク寸前だったらしい。自分の言い方もキツかったと反省。伝え方って本当に大事だな。 引用元:X(旧Twitter)
部下が泣いてしまったら、まずは指導を中断し、場所を変えて冷静に話を聞くことが最優先です。「なぜ泣いているのか」を問い詰めるのではなく、「何か辛いことがあったんだね」と、まずはその感情を受け止めてあげましょう。その涙の裏にある本当の原因を探ることが、問題解決と職場環境改善の第一歩となるのです。
実は部下でなく環境の問題?心理的安全性の低い職場の特徴
部下のメンタルの弱さが目立つ時、私たちはつい「本人の性格や能力の問題だ」と考えがちです。しかし、本当にそうでしょうか?もしかしたら、その原因は本人ではなく、職場環境そのものにあるのかもしれません。特に近年、注目されているのが**「心理的安全性」**という概念です。これが低い職場では、どんなに優秀な人材でも能力を発揮できず、メンタル不調に陥りやすくなります。
心理的安全性とは、「このチームの中では、対人関係のリスク、つまり無知、無能、否定的、邪魔だと思われるような行動をしても、安全であるという信念がメンバー間で共有されている状態」を指します。これは、Googleが数年間にわたる調査「プロジェクト・アリストテレス」の中で見出した、成功するチームの最も重要な要素です。
あなたの職場が、以下の特徴に当てはまっていないかチェックしてみてください。これらは、心理的安全性が低い職場の典型的なサインです。
- 特徴1:質問や相談がしにくい雰囲気 「こんなことも知らないのか?」と思われるのが怖くて、疑問点があっても質問できない。上司が常に忙しそうで、話しかけるタイミングを伺ってしまう。このような職場では、ミスが隠蔽されやすく、大きな問題に発展するリスクがあります。
- 特徴2:失敗が許されず、非難される文化 一度のミスで厳しく叱責されたり、責任を追及されたりする。挑戦した結果の失敗よりも、失敗しないことが重視される。これでは、社員は萎縮してしまい、新しいアイデアや挑戦が生まれなくなります。
- 特徴3:異なる意見や反対意見が歓迎されない 会議で上司の意見に誰も反論しない。空気を読んで、波風を立てないように振る舞うことが常態化している。同調圧力が強く、多様な視点が活かされないため、イノベーションが阻害されます。
- 特徴4:メンバーの貢献が正当に評価・承認されない 誰かが成果を上げても、それがチーム内で共有されたり、称賛されたりすることが少ない。「頑張っても誰も見てくれない」という無力感は、社員のモチベーションを著しく低下させます。
- 特徴5:個人の悪口や噂話が横行している 誰が敵で誰が味方か分からない。陰で誰かの悪口が言われているのを聞くと、「自分も言われているのではないか」と不安になります。このような不信感は、チームワークを根本から破壊します。
もし、あなたの職場にこれらの特徴が一つでも当てはまるなら、部下のメンタルの弱さは、その環境に適応しようとした結果、あるいは耐えきれなくなった結果である可能性が高いです。個人の資質の問題として片付けるのではなく、まずは上司であるあなた自身が、チームの心理的安全性を高めるための行動を起こすことが求められます。具体的な方法は後の章で詳しく解説しますが、まずは「環境が人を作る」という視点を持つことが、問題解決の重要な一歩となります。
それ、パワハラかも?上司が知らないと危険な法的リスク

「部下のためを思って、厳しく指導しているだけだ」――そのように考えている上司の方は少なくないでしょう。しかし、その指導が、あなたの意図とは裏腹に**「パワーハラスメント(パワハラ)」**と認定されてしまうリスクがあることをご存知でしょうか。もしパワハラと認定されれば、あなた個人だけでなく、会社全体が法的な責任を問われ、社会的信用を失うなど、計り知れないダメージを負うことになります。「メンタルが弱い部下がめんどくさい」という感情のままに行動する前に、まずはパワハラに関する正しい知識を身につけ、法的なリスクを理解しておくことが不可欠です。
2020年6月に施行された改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)により、大企業(中小企業は2022年4月から)では職場におけるパワハラ防止措置が事業主の義務となりました。
厚生労働省は、職場のパワハラを以下の3つの要素を全て満たすものと定義しています。
- 優越的な関係を背景とした言動 (例:上司から部下へ、先輩から後輩へ)
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの (例:業務と無関係な私的な悪口、達成不可能なノルマの強制)
- 労働者の就業環境が害されるもの (例:身体的・精神的な苦痛により、能力の発揮に重大な支障が生じること)
ここで重要なのが、**「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」**という部分です。たとえ業務上の指導であっても、そのやり方が社会通念に照らして不適切であれば、パワハラに該当する可能性があります。
【パワハラに該当しうる言動の6類型】
- ①身体的な攻撃: 殴る、蹴る、物を投げつける
- ②精神的な攻撃: 人格を否定するような暴言、長時間にわたる厳しい叱責
- ③人間関係からの切り離し: 隔離、仲間外れ、無視
- ④過大な要求: 到底達成不可能な業務を課す、業務と無関係な私的雑用を強制する
- ⑤過小な要求: 能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる、仕事を与えない
- ⑥個の侵害: プライベートなことに過度に立ち入る
特にメンタルが弱い部下に対しては、②の精神的な攻撃と受け取られやすい言動に注意が必要です。「だからお前はダメなんだ」「やる気あるのか」といった人格を否定する言葉や、他の社員の前で見せしめのように叱責する行為は、指導の範囲を逸脱していると判断される可能性が非常に高いです。
このような事態を避けるためには、指導を行う際に**「事実」と「感情」を切り分ける**ことが重要です。「〇〇というミスがあった。原因は何だと考える?次はどうすれば防げるだろうか?」というように、人格ではなく、起きた事象(事実)に焦点を当てて対話することが、パワハラのリスクを回避し、部下の成長を促すための鉄則です。
-

-
部下が辞める上司の気持ちとは?会社から受ける評価と対処法
2025/7/29
「メンタル弱い部下めんどくさい」悩みが消える育成術5選
- 【育成術①】察する力で変わる!部下の異変に気づく観察力
- 【育成術②】信頼を築く魔法!ヤフーも実践する1on1面談術
- 【育成術③】プライドが高くても響く!『叱らず動かす』指導法
- 【育成術④】逆効果!「頑張れ」より効果的な声かけとNGワード集
- 【育成術⑤】チームで育てる!心理的安全性を高める職場づくり
- 「限界を迎える前に!上司のための相談窓口と活用ポイント
- まとめ|メンタル弱い部下めんどくさい悩みを成長に変える
【育成術①】察する力で変わる!部下の異変に気づく観察力

メンタルが弱い部下への対応で最も重要なスキルは、何か特別なテクニックよりも、まず部下の小さな「変化」に気づく観察力です。多くのメンタル不調は、いきなり深刻な状態になるわけではありません。その前に必ず、何らかの予兆(サイン)が行動や様子に現れます。上司がこのサインを早期に察知し、声をかけることができれば、問題が大きくなる前に対処することが可能です。これは、部下を守るだけでなく、結果的にチームの生産性低下を防ぎ、上司自身の負担を軽減することにも繋がります。
では、具体的にどこを観察すれば良いのでしょうか。ポイントは**「いつもと違う」**という視点です。部下の普段の状態を把握しておき、そこからの変化を見つけるように心がけましょう。
✅ 見た目・様子の変化
- 表情: 明らかに暗い、笑顔が消えた、目の下にクマがある
- 服装: 身だしなみが乱れている、いつも同じ服を着ている
- 態度: 口数が減った(あるいは逆に不自然に増えた)、周囲とのコミュニケーションを避ける、ため息や独り言が増えた
✅ 勤怠の変化
- 遅刻・早退・欠勤: 特に月曜日や週の初めに増えていないか
- 休憩時間: 一人で過ごすことが増えた、時間になっても席に戻らない
- 残業: 以前より効率が落ちて、不必要な残業が増えていないか
✅ 仕事ぶりの変化
- ミスや抜け漏れ: これまでしなかったようなケアレスミスが増えた
- 集中力: ボーっとしている時間が増えた、仕事のスピードが明らかに落ちた
- 報告・連絡・相談: 報連相が減った、あるいは逆に些細なことでも確認を求めてくるようになった
これらの変化は、厚生労働省が示す「ラインによるケア」においても、管理監督者が気づくべきサインとして挙げられています。大切なのは、これらの変化を「やる気がない」「たるんでいる」と主観的に解釈しないことです。あくまで「〇〇という変化が見られる」という客観的な事実として捉えましょう。
そして、変化に気づいたら、タイミングを見計らって声をかけます。 「〇〇さん、最近少し元気がないように見えるけど、何かあった?」 「最近、残業が続いているみたいだけど、業務量で困っていることはないかな?」 ポイントは、決めつけずに、オープンな質問で相手が話しやすい状況を作ることです。決して「悩みがあるんだろう?」と問い詰めてはいけません。相手が話したくなければ、深追いせずに「何かあったらいつでも聞くからね」と伝えるだけで十分です。
日々の挨拶に一言加える、少し雑談をしてみる、といった小さなコミュニケーションの積み重ねが、部下の普段の状態を知り、異変に気づくための土台となります。部下を「観察」することは、監視することではありません。関心を持って見守ることなのです。この小さな習慣が、部下との信頼関係を育み、問題を未然に防ぐ最強のスキルとなります。
【育成術②】信頼を築く魔法!ヤフーも実践する1on1面談術
部下との間に信頼関係を築きたい、でもどうすればいいか分からない…そんな悩みを抱える上司に、ぜひ実践してほしいのが**「1on1ミーティング」**です。これは、多くの先進企業が導入している人材育成の手法で、特にヤフー株式会社(現:LINEヤフー株式会社)が積極的に取り組んでいることで知られています。1on1は、従来の評価面談とは全くの別物です。その目的は、部下の成長を支援し、悩みや課題を共に解決していくことにあります。これを定期的に行うことで、部下は「自分は大切にされている」「この上司は自分のことを分かってくれようとしている」と感じ、メンタルが弱い部下であっても、安心して心を開けるようになります。
ヤフー株式会社では、1on1を「部下の才能と情熱を解き放つ」ための重要な施策と位置づけています。上司が部下の話をじっくりと聞くことで、部下自身が自分の考えやキャリアについて内省し、自律的な成長を促すことを狙いとしています。
では、具体的にどのように進めれば良いのでしょうか。効果的な1on1を実施するためのポイントは以下の通りです。
【1on1ミーティング 成功の5か条】
- 頻度と時間を決めて「定例化」する
- 頻度:週に1回〜隔週に1回が理想。最低でも月に1回は実施しましょう。
- 時間:30分程度でOK。大切なのは長さよりも継続することです。
- 「何かあったら声をかけて」では、メンタルの弱い部下は決して声をかけてきません。上司から定期的な時間を作ることが重要です。
- 主役は「部下」。上司は聞き役に徹する
- 話す割合は**「部下8:上司2」**を意識してください。
- 上司はアドバイスをしたくなりますが、ぐっとこらえて、まずは傾聴に徹します。相槌やうなずき、相手の言葉を繰り返す(「〇〇と感じているんだね」)ことで、「ちゃんと聞いていますよ」というサインを送ります。
- 話すテーマは部下に委ねる
- 業務の進捗確認だけでなく、キャリアの悩み、人間関係、プライベートなことまで、部下が話したいことをテーマにします。
- 「今日は何か話したいことある?」と、まずは部下に問いかけてみましょう。
- 場所と雰囲気づくりを工夫する
- 自席ではなく、会議室やカフェなど、リラックスして話せる環境を選びましょう。
- 対面で座るのではなく、90度の角度で座るなど、圧迫感を与えない工夫も有効です。
- 話した内容は秘密厳守。そして次につなげる
- 1on1で話された個人的な内容は、本人の許可なく他言してはいけません。これが信頼の土台です。
- ミーティングの最後には、「じゃあ、次は〇〇を試してみようか」「来週、その後の経過を聞かせてね」など、具体的な次のアクションを確認し、継続的なサポートの姿勢を見せることが大切です。
実際に1on1を体験した人からは、こんな声も聞かれます。
最初は1on1って何話せばいいんだよ…って思ってたけど、上司が本当にただただ話を聞いてくれて、自分の頭の中が整理されていった。評価される場じゃないって分かってから、安心して本音を話せるようになった気がする。 引用元:X(旧Twitter)
1on1は、すぐに結果が出る特効薬ではありません。しかし、地道に続けることで、部下との間に確かな信頼のパイプを築くことができます。それは、メンタルの弱い部下が安心して働ける土壌となり、ひいてはチーム全体のパフォーマンス向上につなげることができる時間なのです。
【育成術③】プライドが高くても響く!『叱らず動かす』指導法

メンタルが弱い人の中には、実は**「プライドが高い」という特徴を併せ持っているケースが少なくありません。彼らは自己評価が低い一方で、傷つくことを極度に恐れるため、自己防衛のためにプライドという鎧を身につけています。このような部下に対して、正面からミスを指摘したり、厳しい言葉で叱責したりするのは逆効果です。彼らのプライドを傷つけると、心を閉ざして反発するか、さらに深く落ち込んでしまうかのどちらかになってしまいます。では、どうすれば彼らの行動を変え、成長を促すことができるのでしょうか。その鍵は「叱る」のではなく「動かす」**という発想の転換にあります。
ここで有効なのが、**「I(アイ)メッセージ」と「You(ユー)メッセージ」**の使い分けです。
- Youメッセージ: 「君はなぜ報告しなかったんだ!」「君のやり方は間違っている」のように、相手(You)を主語にして、相手を評価・批判する伝え方。プライドの高い部下は、これを「攻撃」と受け取ります。
- Iメッセージ: 「報告がなくて、私は心配したよ」「こうしてくれると、私はとても助かるな」のように、自分(I)を主語にして、自分の気持ちや状況を伝える方法。相手を非難するニュアンスがなくなるため、素直に受け入れやすくなります。
例えば、報告が遅れた部下に対して、 ❌ Youメッセージ: 「なんでいつも報告が遅いの?社会人として基本でしょ!」 ✅ Iメッセージ: 「〇〇の件、進捗が分からなくて、私は少し心配していたんだ。もし何か困っていることがあれば、早めに相談してくれると、私もサポートしやすいから助かるな。」
このように伝えることで、部下は「責められた」ではなく「心配してくれている」「頼られている」と感じ、次からの行動を変えようという気持ちになりやすくなります。
さらに、具体的な行動を促すためには、サンドイッチ話法も効果的です。
【サンドイッチ話法の実践例】
- 【パン】褒める・認める(クッション言葉) 「いつも資料作成、丁寧に進めてくれてありがとう。〇〇さんの作る資料は見やすいと評判だよ。」
- 【具】改善してほしい点(Iメッセージで伝える) 「その上で一つお願いがあるんだけど、提出前に一度、誤字脱字のセルフチェックをしてもらえると、私はもっと安心してクライアントに提出できるから、すごく助かるな。」
- 【パン】期待・励まし(未来志向の言葉) 「この一手間を加えることで、〇〇さんの資料はもっと完璧になると思うよ。期待しているね!」
この手法は、最初に肯定的な言葉で入ることで、相手が心のガードを下ろし、本題である改善点を素直に聞き入れやすくする効果があります。
プライドの高い部下を動かすのは、権力や正論ではありません。相手への敬意を示し、こちらの要望を「お願い」として伝えるという、丁寧なコミュニケーションです。「叱って矯正する」という考え方を手放し、「どうすれば気持ちよく動いてくれるか」という視点に立つことが、彼らの高いプライドを味方につけ、成長へと導くための最も賢明な指導法なのです。
【育成術④】逆効果!「頑張れ」より効果的な声かけとNGワード集
部下が落ち込んでいる時や、仕事に苦戦している時、良かれと思って「頑張れ!」と声をかけていませんか?実はこの一言、メンタルが弱っている人にとっては、大きなプレッシャーとなり、逆効果になることが少なくありません。本人は既に精一杯頑張っているのに、これ以上何を頑張ればいいのかと追い詰められたり、「自分の頑張りが足りないと責められている」と感じてしまったりするのです。部下の心を軽くし、前向きな気持ちを引き出すためには、「頑張れ」という漠然とした激励ではなく、より具体的で、相手に寄り添った声かけが求められます。
厚生労働省のメンタルヘルス関連情報でも、うつ病の可能性がある人への「激励」は禁句とされています。これは、本人の焦燥感を強めてしまうためです。では、「頑張れ」の代わりに、どのような言葉をかければ良いのでしょうか。状況に応じた効果的な声かけの例を以下に示します。
【「頑張れ」の言い換えフレーズ集】
- プロセスを承認する声かけ
- 「いつも遅くまで頑張っているね。ちゃんと見ているよ。」
- 「〇〇の準備、大変だったでしょう。よくやったね。」
- ポイント: 結果だけでなく、そこに至るまでの努力や過程を具体的に認めることで、部下は「自分のことを見てくれている」と安心します。
- 負担を軽くする声かけ
- 「一人で抱え込まないで、何か手伝えることはある?」
- 「その仕事、少し分担しようか。」
- 「今日はもう休んだら?無理はしないでね。」
- ポイント: 精神的なサポートだけでなく、物理的な負担を軽減する提案は、非常に効果的です。
- 気持ちに寄り添う声かけ
- 「大変だったね」「辛かったね。」
- 「無理もないよ。私でもそう思うよ。」
- ポイント: アドバイスや解決策を示す前に、まずは相手の感情を肯定し、共感する姿勢を見せることが、信頼関係の第一歩です。
- 休息を促す声かけ
- 「しっかり休むのも大切な仕事だよ。」
- 「少し休憩して、気分転換してきたら?」
- ポイント: 「休むことへの罪悪感」を和らげ、心身の回復を促します。
一方で、良かれと思って使ってしまいがちなNGワードも存在します。これらの言葉は、部下をさらに追い詰める可能性があるので、注意が必要です。
【要注意!メンタル不調の部下へのNGワード集】
| NGワード | なぜNGか |
|---|---|
| 「頑張れ」「しっかりしろ」 | これ以上何を頑張ればいいのかと、本人を追い詰める。 |
| 「なんでできないんだ」 | 能力を否定し、自己肯定感をさらに下げる。 |
| 「気にしすぎだよ」「考えすぎだよ」 | 悩みを軽視し、本人の辛さを否定することになる。 |
| 「もっと大変な人もいる」 | 他人と比較することで、本人の苦しみを矮小化してしまう。 |
| 「いつ治るの?」 | 回復を焦らせ、プレッシャーを与える。 |
大切なのは、部下を「変えよう」とするのではなく、**「ありのままを受け入れる」**というスタンスです。あなたの温かい言葉かけ一つが、部下にとっては暗闇の中の一筋の光となり、再び立ち上がるための大きな力となるのです。
【育成術⑤】チームで育てる!心理的安全性を高める職場づくり

メンタルの弱い部下への対応は、上司一人が背負うべき問題ではありません。もし、あなたが一人で抱え込み、その部下だけを特別扱いしようとすると、他のメンバーから「不公平だ」という不満が生まれ、チーム全体のバランスが崩れてしまいます。真の解決策は、チーム全体でメンバーを支え、育てる文化を醸成すること、すなわち**「心理的安全性」の高い職場**を作ることです。心理的安全性が確保されたチームでは、メンバーは互いを尊重し、助け合うことが当たり前になります。その結果、メンタルの弱い部下も孤立することなく、安心して自分の能力を発揮できるようになるのです。
心理的安全性を高めるために、上司として明日から実践できる具体的なアクションを5つ紹介します。
- 「発言の機会」を均等に与える 会議などで、特定の人ばかりが話していませんか?「〇〇さんは、この件についてどう思う?」と、普段あまり発言しないメンバーに意識的に話を振ることで、「自分の意見も尊重されるんだ」という安心感を与えます。全員が参加者であるという意識を育てることが重要です。
- 上司自ら「自己開示」をする 上司が完璧である必要はありません。「実は私も昔、同じようなミスをしてね…」「この分野は苦手で、〇〇さんに教えてほしいな」というように、自らの弱みや失敗談をオープンにすることで、親近感が湧き、部下も自分の弱みを話しやすくなります。上司の完璧さよりも、人間らしさを見せることが、風通しの良い雰囲気を作ります。
- 「感謝」と「称賛」を言葉にする文化を作る 「〇〇さん、あの件フォローしてくれてありがとう!」「そのアイデア、素晴らしいね!」など、ポジティブな行動に対して、すぐに言葉でフィードバックすることを習慣化しましょう。上司からだけでなく、メンバー同士でも自然に感謝を伝え合えるような雰囲気を作ることが理想です。これを「サンクスカード」などの仕組みとして導入している企業もあります。
- 「挑戦した結果の失敗」を許容し、次に活かす ミスが起きた時に、犯人探しや叱責をするのではなく、「なぜこのミスが起きたんだろう?」「次に同じことを起こさないためには、どういう仕組みが必要かな?」と、未来志向の対話を心がけましょう。「失敗は学びの機会である」というメッセージをチーム全体で共有することで、メンバーは萎縮することなく、新しいことに挑戦できるようになります。
- チームの目標やビジョンを共有し、一体感を醸成する 「私たちは何のためにこの仕事をしているのか」「このチームはどこを目指しているのか」という共通の目的意識は、強力な一体感を生み出します。個々の業務が、チーム全体の大きな目標にどう繋がっているのかを明確にすることで、メンバーは自分の仕事に誇りを持ち、互いに協力し合うようになります。
心理的安全性の高い職場は、一朝一夕には作れません。しかし、上司であるあなたが、これらのアクションを意識して率先して行うことで、少しずつチームの空気は変わっていきます。一人の部下を「点」で支えるのではなく、チームという「面」で支える。その環境づくりこそが、上司に課せられた最も重要な役割であり、あらゆる問題の根本的な解決策となるのです。
「限界を迎える前に!上司のための相談窓口と活用ポイント

部下のメンタルヘルス対応に奮闘する中で、「もう自分だけでは限界だ…」と感じる瞬間が来るかもしれません。そのように感じたら、決して一人で抱え込まないでください。上司自身が心身のバランスを崩してしまっては、元も子もありません。幸い、現代の日本には、管理職が利用できる社内外の相談窓口が整備されています。これらのリソースを積極的に活用することは、決して逃げではなく、部下と自分自身、そして会社全体を守るための賢明な判断です。ここでは、主な相談窓口とその活用ポイントについて解説します。
【社内の相談窓口】
- 人事・労務部門
- 役割: 社員のメンタルヘルス対策の中心となる部署です。就業規則や社内制度に精通しており、具体的な対応策(休職手続き、産業医面談の設定など)について相談できます。
- 活用ポイント: 部下の勤怠に明らかな変化が見られる、休職の可能性がある、といった具体的な状況になった場合に、まず相談すべき相手です。対応に困った際の「公式な相談相手」として、密に連携を取りましょう。
- 産業医・保健師
- 役割: 医学的な見地から、社員の健康管理をサポートする専門家です。部下の健康状態に関する助言や、本人との面談を通じたケアを行ってくれます。
- 活用ポイント: 「これは甘えか、不調か」の判断に迷った時や、部下に受診を勧めたいがどう切り出せばいいか分からない時などに相談しましょう。守秘義務があるため、上司が直接部下の診断内容を聞くことはできませんが、今後の就業上の配慮について専門的なアドバイスをもらえます。
【社外の相談窓口】
- EAP(従業員支援プログラム)
- 役割: 会社が契約している外部のカウンセリングサービスです。社員本人だけでなく、その家族や管理職からの相談も受け付けている場合があります。
- 活用ポイント: 匿名で相談できることが多く、「社内の人には話しにくい」と感じる内容(例:部下との人間関係の悩み、自身のストレスなど)を相談するのに適しています。自社に導入されているか、人事部門に確認してみましょう。
- 厚生労働省「こころの耳」
- 役割: 働く人のメンタルヘルスに関する情報を集約したポータルサイトです。電話やSNSでの相談窓口も設けており、事業者(管理職)からの相談も受け付けています。
- 活用ポイント: 職場のメンタルヘルス対策に関する基本的な知識を得たい時や、公的な相談窓口を知りたい時に非常に役立ちます。ウェブサイトには、管理職向けの研修資料なども豊富に掲載されています。
これらの窓口に相談する際は、具体的な事実を整理しておくことが重要です。
- いつから、どのような変化が見られるか(勤怠、仕事のミス、言動など)
- これまで、どのような対応をしてきたか(声かけ、面談など)
- 現在、何に一番困っているか
これらの情報をまとめておくことで、相談がスムーズに進み、より的確なアドバイスを得ることができます。部下の問題は、あなた一人の問題ではありません。専門家の力を借りることは、より良い解決への近道であり、あなた自身を守るためのセーフティネットなのです。
まとめ|メンタル弱い部下めんどくさい悩みを成長に変える

この記事では、「メンタル弱い部下めんどくさい」という悩みの根本原因から、明日から使える具体的な育成術までを詳しく解説してきました。最後に、今回の内容を振り返りましょう。
まず、部下に対して「めんどくさい」と感じてしまうのは、上司として自然な感情であり、決してあなたが冷たいわけではない、ということをお伝えしました。その感情の裏には、Z世代との価値観のギャップや、心理的安全性が低い職場環境など、様々な要因が隠れています。部下の行動を「甘え」と決めつける前に、その背景にある**「不調のサイン」や「SOS」**を正しく見極めることが重要です。
そして、その悩みを解決するための具体的な育成術として、以下の5つをご紹介しました。
- 【観察力】: 「いつもと違う」という小さな変化に気づくことが、すべての始まりです。
- 【1on1面談】: 部下の話を「聞く」ことに徹する時間が、信頼関係を築きます。
- 【叱らず動かす指導法】: 「Iメッセージ」を使い、相手のプライドを尊重しながら行動を促します。
- 【効果的な声かけ】: 「頑張れ」ではなく、具体的なプロセス承認や共感の言葉を選びます。
- 【チームで育てる】: 上司一人で抱え込まず、心理的安全性の高いチーム全体で支える文化を作ります。
また、どうしても限界を感じた時には、人事部門や産業医、EAPなどの専門窓口に相談するという選択肢があることも忘れないでください。
「メンタルが弱い部下」は、見方を変えれば**「繊細な感性を持ち、真面目で、誠実な部下」**であるとも言えます。彼らが安心して能力を発揮できる環境を整えることができれば、その繊細さは、他の人が気づかないような細やかな気配りや、丁寧な仕事ぶりとして、チームにとって大きな強みとなるでしょう。
今回の記事で紹介したアプローチは、一見、遠回りに見えるかもしれません。しかし、部下一人ひとりと真摯に向き合い、信頼関係を築いていくことこそが、結果的にチームの生産性を最大化し、あなた自身のマネジメント能力を飛躍的に高める最も確実な道なのです。
「めんどくさい」という感情を、部下とチームを成長させるためのエネルギーに変えて、今日から何か一つでも、新しいアクションを始めてみてはいかがでしょうか。
-

-
【イライラ解消】業務を止めない!職場で泣くおばさんの対応策
2025/8/13