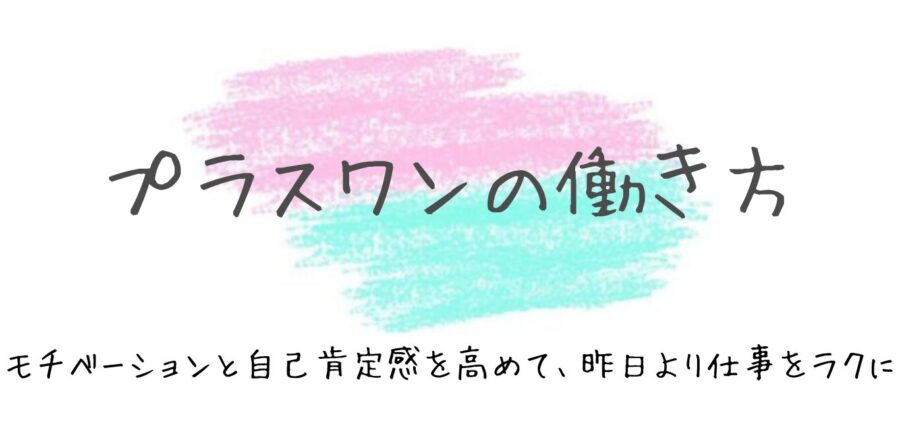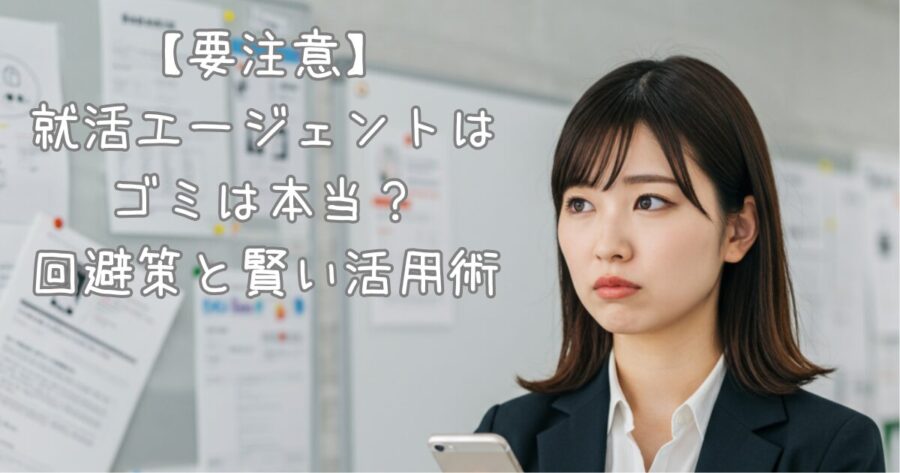「なんで自分ばかり仕事が増えるんだ…」
「あの人のミスのフォロー、もうやりたくない…」
仕事ができない人のフォローを続けるうちに、日に日に増していくその疲れとストレス。真面目で責任感の強いあなただからこそ、一人で抱え込み、心身ともに限界を感じているのではないでしょうか。
その悩み、決してあなたの心が狭いわけでも、能力が低いわけでもありません。
実は、その「疲れ」は個人の問題だけでなく、職場の環境や構造的な問題が原因であることがほとんどです。この記事では、なぜあなたが疲れてしまうのか、その根本原因を解き明かします。
さらに、厚生労働省のデータや具体的な事例を基に、明日から実践できる心を救うための具体的な対処法を徹底解説。
この記事を最後まで読めば、あなたが今抱えている重荷を下ろし、自分らしく健全に働くための道筋が必ず見えてきます。もう一人で悩むのは、今日で終わりにしましょう。
目次
もう限界!仕事できない人のフォローに疲れるあなたへ
- 「また自分の仕事が…」フォローばかりで募る不公平感
- なぜか仕事できない人が上司に守られる職場の理不尽
- 終わらないミスのフォロー地獄…能力不足へのイライラ
- 時短や休む同僚のフォローまで…善意が搾取される構造
- その疲れは危険信号!心が壊れる前に知るべきこと
- 原因は本人だけじゃない?会社組織に潜む隠れた問題
- あなたの「疲れた」は甘えじゃない!当然の感情です
「また自分の仕事が…」フォローばかりで募る不公平感
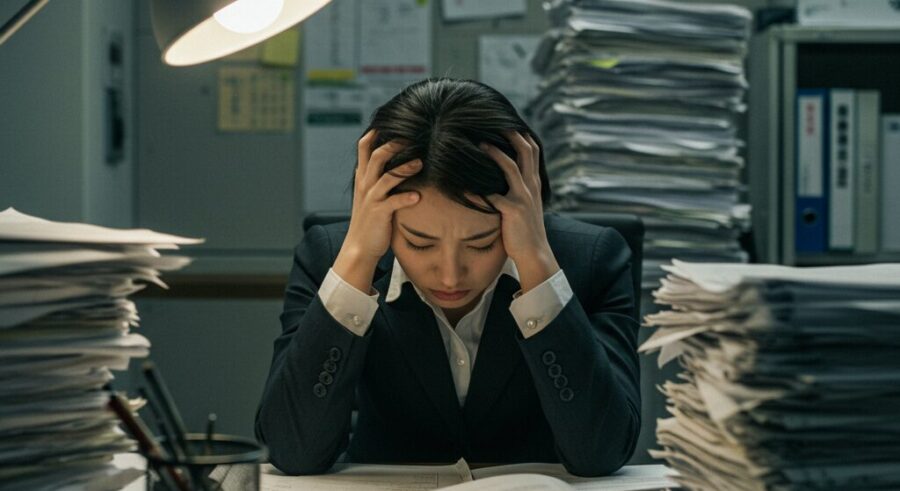
「この作業、私がやるべきことなのだろうか…」と感じながら、同僚の終わらなかった仕事やミスの後始末に追われる日々。あなたの貴重な時間とエネルギーが、他人のためにどんどん奪われていく感覚に陥っていませんか。この**「フォローばかり」の状況が引き起こす最も大きな問題は、深刻な不公平感**です。
同じ給料をもらっているはずなのに、なぜか自分だけが多くの責任と業務量を背負わされている。この状況は、仕事へのモチベーションを著しく低下させます。最初は「お互い様だから」と親切心で始めたフォローも、いつしか当たり前になり、感謝の言葉すらなくなることも珍しくありません。
✅ あなたのタスクが後回しになる
✅ フォローした仕事で評価されるのは本人
✅ 残業時間が増え、プライベートが犠牲になる
✅ 「ありがとう」の一言もなく、虚しさを感じる
このような状況が続くと、徐々に「どうして自分だけが損をしているんだ」という怒りや不満が心の中に蓄積されていきます。この感情は、職場の人間関係にも悪影響を及ぼしかねません。
実際に、SNS上でも同じような悩みを抱える声が多く見られます。
同僚の仕事のミスのフォローとか尻拭いとか、こっちの仕事増やされるの本当に腹立つ。できないならできないなりに努力してほしい。周りがフォローしてくれるの当たり前だと思わないでほしい。今日も私含め3人が尻拭いさせられて残業。本人はさっさと帰宅。本当に腹立つ。引用元:X(旧Twitter)
この不公平感は、単なる感情の問題では済まされません。放置すれば、あなたの仕事の質そのものにも影響を与え始めます。自分の本来の業務に集中できず、中途半端な成果しか出せなくなる恐れさえあります。その結果、あなた自身の評価が下がるという、本末転倒な事態に陥る可能性も否定できません。まずは、この不公平な状況に気づき、それが当たり前ではないと認識することが、問題解決の第一歩となるでしょう。
なぜか仕事できない人が上司に守られる職場の理不尽
「あの人はあんなにミスが多いのに、なぜか上司は強く注意しない…」
「むしろ、フォローしている自分の方が『もっと上手くやってくれ』と言われる…」
このような理不尽な経験はありませんか。本来であれば、パフォーマンスが低い社員を指導・育成するのが上司の役割です。しかし、現実には仕事ができない人ほど上司に守られ、真面目にフォローしている側が割を食うという、信じがたい状況が多くの職場で発生しています。
この現象が起こる背景には、いくつかの組織的な理由が考えられます。
- 波風を立てたくない事なかれ主義の上司
- 問題社員に強く指導すると、反発されたり、ハラスメントだと騒がれたりするリスクを恐れている。
- 面倒な事態を避け、平穏を保つために、問題から目をそらしているのです。
- 「できる人」への過度な依存
- 上司は「あなたなら何とかしてくれるだろう」と、あなたの能力と責任感に甘え、問題解決を丸投げしている。
- 結果的に、あなたがいればチームは回ると錯覚し、根本的な問題(仕事のできない人)に対処しようとしません。
- 評価制度の欠陥
- 個人の成果よりも、チーム全体の数字や協調性を重視する評価制度の場合、個々のパフォーマンスの差が見えにくくなる。
- 問題を隠して穏便に済ませることが、上司自身の評価に繋がっているケースもあります。
このような状況は、フォローしているあなたにとって「はしごを外された」ような感覚に陥らせます。頑張れば頑張るほど、自分の立場が悪くなるように感じ、会社や上司に対する信頼を失っていくでしょう。
仕事できない人って謎に自己肯定感高くて上司とかに守られてるからほんとに厄介。こっちがフォローしてんのにそんなことも知らないで...。引用元:X(旧Twitter)
この理不尽な構造の中で、あなたが一人で頑張り続ける必要は全くありません。 問題は、仕事ができない同僚個人だけでなく、それを許容し、あなたに負担を押し付けるマネジメント、つまり上司や会社の体制にあることを理解することが重要です。この認識を持つことで、次に取るべき行動がより明確になります。
終わらないミスのフォロー地獄…能力不足へのイライラ

「何度同じことを教えれば覚えるんだろう…」
「この単純なミスで、どれだけの人が迷惑を被っていると思っているのか…」
仕事ができない人の最も顕著な特徴の一つが、繰り返される単純なミスや、業務理解度の低さです。その一つ一つのミスは小さくても、積み重なれば大きな手戻りや時間のロスにつながり、そのフォローはすべて周囲の社員、特にあなたの肩にのしかかってきます。
この「終わらないミスのフォロー地獄」は、あなたの精神を確実に蝕んでいきます。
- 原因究明と修正作業に忙殺される
- どこで間違えたのかを探し出し、正しい状態に戻す作業は、本来の業務よりもはるかに神経を使います。
- 顧客や他部署への謝罪
- ミスによっては、あなたが直接の担当者ではないにもかかわらず、頭を下げなければならない場面も出てくるでしょう。
- スケジュールの遅延と再調整
- 一つのミスが原因でプロジェクト全体の進行が遅れ、関係各所との面倒な調整作業が発生します。
こうした状況が続くと、当初の「助けてあげよう」という気持ちは消え失せ、「なぜこんなこともできないんだ」という純粋な能力不足へのイライラへと変わっていきます。このイライラは、人間関係を悪化させるだけでなく、あなた自身の集中力を削ぎ、パフォーマンスを低下させる原因にもなりかねません。
リクルートが運営するメディアの記事でも、ローパフォーマー(成果を出せない社員)の特徴として「業務遂行能力が低い」「同じミスを繰り返す」といった点が挙げられており、これは多くの企業で共通する課題であることがわかります。
重要なのは、相手の能力不足をあなたが補い続ける義務はない、という事実です。ミスのフォローは、あくまで一時的な応急処置に過ぎません。根本的な解決のためには、本人にミスを自覚させ、改善を促す仕組みが必要です。あなたが一人で抱え込み、イライラを募らせることは、誰にとっても良い結果を生まないのです。
時短や休む同僚のフォローまで…善意が搾取される構造

「時短勤務だから、残りの業務をお願いできますか?」
「体調不良で休むので、急ぎの件、対応しておいてもらえますか?」
もちろん、子育てや介護、体調不良など、様々な事情で時短勤務を選択したり、急に仕事を休んだりするのは誰にでも起こりうることです。互いに助け合うのは当然の文化であり、それ自体は素晴らしいことに違いありません。
しかし、問題はそのフォローが特定の人、つまりあなたにばかり集中してしまうことです。
「あの人に頼めば、何とかしてくれる」
「あの人はいつも快く引き受けてくれる」
あなたの優しさや責任感の強さが、周囲から「便利な存在」として認識されてしまうと、善意が一方的に搾取される構造が生まれます。本来であれば、誰かが抜けた穴はチーム全体でカバーすべきであり、そのための人員配置や業務分担を考えるのは管理職の仕事です。
✅ 常に誰かの「代理」業務に追われる
✅ 自分の仕事が定時内に終わらない
✅ 「ありがとう」と言われるが、負担は増える一方
✅ 断ると「冷たい人」だと思われるのではないかと不安になる
この「善意の搾取」構造は、非常に根深い問題です。なぜなら、あなたの「助けてあげたい」というポジティブな感情につけ込んでいるため、断ることに罪悪感を抱きやすいからです。しかし、その結果、あなたの心と体はどんどん疲弊していきます。
厚生労働省の調査でも、職場のストレス原因として「仕事の量」と並んで「対人関係」が常に上位に挙げられています。一見、助け合いに見えるフォロー業務も、バランスが崩れれば深刻なストレス源となりうるのです。
あなたの善意は決して安売りされるべきではありません。チームへの貢献と、自己犠牲は全くの別物です。もし、特定の人のフォローが常態化し、それがあなたの大きな負担になっているのであれば、それはチーム全体で解決すべき「業務プロセスの問題」として捉え直す必要があります。
その疲れは危険信号!心が壊れる前に知るべきこと

「最近、何だかやる気が出ない…」
「休日も仕事のことばかり考えてしまい、心が休まらない…」
「以前は楽しかった趣味にも興味がなくなった…」
もし、あなたがこのような状態にあるなら、それは単なる「疲れ」ではなく、心が発している危険信号、つまり「バーンアウト(燃え尽き症候群)」の一歩手前かもしれません。
バーンアウトとは、持続的な職務上のストレスが原因で、情緒的な消耗感、脱人格化(顧客や同僚への思いやりの喪失)、個人的達成感の低下を主症状とする状態です。特に、仕事ができない人のフォローのように、終わりが見えないまま他者のためにエネルギーを注ぎ続ける状況は、バーンアウトに陥る典型的なパターンの一つです。
以下の項目に、当てはまるものがないかセルフチェックしてみましょう。
- 情緒的消耗感
- 朝、仕事に行こうとすると心身ともに疲れ果てていると感じる。
- 仕事が終わると、何もする気力が残っていない。
- ささいなことでイライラしたり、感情的になったりする。
- 脱人格化
- 同僚や顧客に対して、以前より冷淡な態度をとってしまう。
- 相手を「モノ」のように感じ、思いやりを持てなくなる。
- 職場の人間と距離を置きたくなる。
- 個人的達成感の低下
- 仕事で何かを成し遂げても、達成感や満足感を得られない。
- 自分の仕事に価値があるとは思えなくなる。
- 「自分はダメだ」と自己評価が著しく低くなる。
もし3つ以上当てはまるようなら、注意が必要です。独立行政法人 労働政策研究・研修機構の資料においても、バーンアウトは個人の問題だけでなく、職場の環境、特に「仕事の量的負担」や「コントロールの低さ」「社会的支援の乏しさ」が大きく関与すると指摘されています。
仕事ができない人のフォローは、まさに「仕事の量的負担」が増え、「自分で業務をコントロールできず」、周囲からの「十分な支援(感謝や正当な評価)が得られない」という、バーンアウトのリスクが非常に高い状況と言えるでしょう。
あなたの心と体は、あなたが思っている以上に限界に近づいているかもしれません。「まだ大丈夫」と自分に言い聞かせるのをやめ、まずは自分自身の状態を客観的に把握することが、心が壊れるのを防ぐための最も重要なステップです。

原因は本人だけじゃない?会社組織に潜む隠れた問題
あなたがこれほどまでに疲弊している原因は、本当に「仕事ができない同僚」だけにあるのでしょうか。実は、より深く見ていくと、個人をそうさせてしまう会社組織そのものの問題が浮かび上がってきます。
多くの場合、パフォーマンスの低い社員が存在する背景には、以下のような組織的な問題が隠れています。
- 1. 明確な役割分担の欠如
- 「誰が」「何を」「どこまで」やるのかが曖昧なため、仕事の押し付け合いが発生しやすい。
- 日本の多くの企業が採用する「メンバーシップ型雇用」では、ジョブディスクリプション(職務記述書)が不明確なため、この問題が起きがちです。
- 2. マネジメントの機能不全
- 部下の業務量や進捗状況を正確に把握できていない。
- 問題を発見しても、具体的な指導や介入を行わず、現場に丸投げしている。
- 本来、パフォーマンス管理はマネージャーの最重要業務の一つです。
- 3. 不適切な人員配置(ミスマッチ)
- 本人の適性や能力を無視した部署に配置されている。
- 本人は「やりたい」「できる」と思っていても、客観的に見てその業務に向いていないケースです。これは本人の責任だけでなく、適材適所を実現できていない人事部の問題でもあります。
- 4. 形骸化した人事評価制度
- 成果や貢献度が正しく評価に反映されないため、頑張っても報われない。
- 逆に、仕事ができなくても給料が下がらないため、本人が問題意識を持つ機会を奪っています。
- 5. 十分な教育・研修の不足
- OJT(On-the-Job Training)が名ばかりで、体系的な教育が行われていない。
- 見て覚えろ、という古い体質の職場では、成長できる人とできない人の差が顕著になります。
このように、あなたが直面している問題は、氷山の一角に過ぎません。その水面下には、会社組織の様々な構造的問題が横たわっています。この視点を持つことで、「なぜ自分がこんな目に…」という個人的な悩みから、「この会社の仕組み自体がおかしいのではないか」という、より本質的な問題意識へと変わるはずです。そしてそれは、あなたが会社に対して具体的な改善を働きかける際の、強力な論拠にもなり得ます。
あなたの「疲れた」は甘えじゃない!当然の感情です

ここまで、仕事ができない人のフォローによって生じる様々な問題点を見てきました。不公平感、理不尽な上司、終わらないミスのフォロー、善意の搾取、そして会社組織の問題…。
これだけの重圧がのしかかっているのです。あなたが「疲れた」と感じるのは、決して甘えや根性不足などではありません。それは、人間としてあまりにも当然で、健全な感情なのです。
むしろ、この状況で「疲れた」と感じない方が不自然だと言えるでしょう。あなたはこれまで、自分の責任感と優しさから、本來負う必要のないはずの責任まで背負い、歯を食いしばって頑張ってきたのではないでしょうか。
✨ 自分の感情を、まずは自分で認めてあげましょう。
✨ 「よくここまで頑張ってきた」と、自分を褒めてあげてください。
この「感情の肯定」は、次の一歩を踏み出すためのエネルギーを充電するために、非常に重要なプロセスです。自分を責めるのをやめ、客観的な事実として「自分は今、疲弊している」と認識することで、初めて具体的な解決策に目を向けることができます。
多くの人が、「自分が我慢すれば丸く収まる」と考えがちです。しかし、あなたが我慢し続けた結果、心身のバランスを崩してしまっては、元も子もありません。そうなってからでは、回復に長い時間が必要になることもあります。
現在の日本社会では、働く人の多くが様々な悩みを抱えており、あなたが特別なわけではないのです。
この記事を読んでいる今この瞬間が、あなたの状況を変える絶好のタイミングです。次の章では、この「疲れ」から抜け出し、自分自身を守るための具体的な対処法を詳しく解説していきます。もう一人で抱え込む必要はありません。一緒に、この問題を解決していきましょう。
-

-
【要注意】就活エージェントはゴミは本当?回避策と賢い活用術
2025/9/7
「仕事できない人のフォローが疲れる」を断ち切る対処法
- まず自分を守る!「関わりたくない」は悪いことじゃない
- 角を立てずに仕事を分担する魔法のコミュニケーション術
- 上司を味方に!状況を動かすための戦略的な相談方法
- 「ここまでしかやらない」物理的な境界線を引く勇気
- イライラをリセット!仕事中にできる心を保つ応急処置
- もう我慢しない!先輩・同僚への賢い関わり方とは?
- 全ての対処法が無理なら…環境を変えるという選択肢
まず自分を守る!「関わりたくない」は悪いことじゃない

あらゆる対処法の前提として、最も重要で、最初に持つべき心構え。それは**「まず自分自身を守る」という意識**です。
これまであなたは、チームのため、会社のためにと、自己犠牲を払ってフォローを続けてきたかもしれません。しかし、その結果あなたが疲弊し、潰れてしまっては、誰のためにもなりません。まずは、自分を最優先に考える許可を自分自身に出してあげましょう。
そして、その中で芽生える「あの人とは、仕事上あまり関わりたくない」という感情。これは決して悪いことではなく、むしろあなたの心が発している健全な防衛本能なのです。
人間関係には相性がありますし、仕事の進め方や価値観が合わない人と無理に関わり続けることは、多大な精神的エネルギーを消耗します。そのエネルギーは、本来あなたのやるべき業務や、あなた自身の成長のために使うべきものです。
✅ 罪悪感を手放す
* 「冷たい」「非協力的だ」と思われることを恐れる必要はありません。あなたの心とキャリアを守るための、正当な自己防衛です。
✅ 物理的な距離を取る
* 可能であれば、座席を移動させてもらう、コミュニケーションをチャットやメール中心にするなど、物理的に距離を置く工夫も有効です。
✅ 心理的な境界線(バウンダリー)を引く
* 「相手の問題は相手の問題、自分の問題は自分の問題」と心の中で線引きをします。相手の機嫌や成長まで、あなたが背負う必要はありません。
この「自分を守る」という覚悟が、これから紹介する具体的なアクションを実践する上での土台となります。パナソニック ホールディングス株式会社の創業者である松下幸之助氏も、社員の自主性を重んじたことで知られています。あなた自身の仕事に対する自主性や裁量権を守ることは、決してわがままではないのです。
仕事できない人と関わりたくないって思うの、全然悪いことじゃないよね。今まで無理して関わって、こっちが病みそうだった。最近は意識的に距離置くようにしたら、メンタルがめちゃくちゃ安定してる。自分を守るって大事。引用元:X(旧Twitter)
「関わりたくない」と思う自分を責める必要は一切ありません。それは、あなたがこれまで頑張ってきた証拠であり、自分自身を大切にしようとしている証拠なのです。この強い意志を持って、次のステップに進んでいきましょう。
角を立てずに仕事を分担する魔法のコミュニケーション術
「自分を守る」と決めても、いきなり「あなたの仕事は手伝いません」と突き放すのは、職場の人間関係を考えると現実的ではありません。そこで重要になるのが、相手を不快にさせずに、かつ自分の負担を減らすコミュニケーション術です。
ここでは、明日からすぐに使える3つの魔法の言い回しとテクニックを紹介します。
1. 「I(アイ)メッセージ」で自分の状況を伝える
「You(あなた)はなぜできないの?」と相手を主語にすると、非難しているように聞こえてしまいます。そうではなく、「I(私)」を主語にして、自分の状況や気持ちを客観的に伝えましょう。
- NG例: 「(あなたは)なんでいつも締め切りを守れないんですか?こっちが迷惑です」
- OK例: 「(私は)今、別の急ぎの案件を抱えていて、もしこの作業が遅れると(私が)困ってしまうんだ。何か手伝えることはあるかな?」
このように伝えることで、相手を責めるニュアンスがなくなり、「協力して問題を解決しよう」という前向きな姿勢を示すことができます。
2. DESC(デスク)法で論理的に依頼する
感情的にならず、冷静に依頼したいときに非常に有効なフレームワークがDESC法です。
- D (Describe): 描写する
- 客観的な事実だけを伝えます。「〇〇の資料、3回連続で計算ミスがあるみたいなんだ」
- E (Express/Explain): 表現・説明する
- 自分の意見や気持ちを伝えます。「修正に時間がかかって、私のタスクが少し遅れ気味で困っているんだ」
- S (Specify/Suggest): 提案する
- 具体的な解決策を提案します。「今後、入力が終わったら一度ダブルチェックをお願いできないかな?」
- C (Choose/Consequence): 選択・結果を伝える
- 相手が提案を受け入れた場合と、受け入れなかった場合の結果を示します。「もしお願いできれば、全体の進行がスムーズになると思うんだ。もし難しいなら、一度〇〇さん(上司)に相談してみようか」
この順番で話すことで、あなたの要求が非常に論理的で、かつ相手にも選択肢を与える丁寧な依頼に聞こえます。
3. 「クッション言葉」をフル活用する
依頼や断りを入れる際に、本題の前に一言添えるだけで、印象は劇的に和らぎます。
- 「**お手数をおかけして申し訳ないのですが、**~」
- 「**大変恐縮なのですが、**~」
- 「**ご期待に沿えず申し訳ないのですが、**今は手一杯で…」
これらの言葉を枕詞として使うことで、相手への配慮を示し、スムーズな人間関係を維持しながら、自分の主張をしっかりと伝えることが可能になります。
これらのコミュニケーション術は、一朝一夕で完璧にできるものではありません。しかし、意識して使い続けることで、あなたの負担は確実に減っていきます。言葉一つで、あなたの職場環境は変えられるのです。
上司を味方に!状況を動かすための戦略的な相談方法

同僚への直接的なアプローチと並行して、あるいはそれが難しい場合に絶対に行うべきなのが、上司への相談です。しかし、この相談が単なる「愚痴」や「告げ口」になってしまうと、逆効果になりかねません。「あいつは協調性がない」と、あなた自身の評価を下げてしまう危険性もあります。
そうならないために、上司をあなたの**「問題解決のパートナー」として巻き込むための、戦略的な相談方法を身につけましょう。重要なのは、感情ではなく事実(ファクト)**に基づいて話すことです。
ステップ1:相談前の準備(証拠集め)
上司に相談する前に、客観的な事実を整理しておきましょう。記憶だけに頼らず、具体的な記録を残しておくことが重要です。
- 具体的な事実の記録
- いつ、誰が、どのようなミスをしたか
- そのフォローに、あなたがどれくらいの時間を使ったか
- その影響で、あなたの本来の業務がどれだけ遅れたか
- (可能であれば)関連するメールやチャットの履歴
これらの記録は、あなたの主張が感情的なものではなく、業務上の具体的な問題であることを示す強力な証拠となります。
ステップ2:相談のアポイントと切り出し方
いきなり話しかけるのではなく、「業務の進め方について、少しご相談したいことがあるのですが、15分ほどお時間をいただけないでしょうか?」と、事前にアポイントを取りましょう。これにより、上司も話を聞く心構えができます。
切り出す際は、個人攻撃にならないよう注意が必要です。
- NG例: 「〇〇さんが仕事できなくて困ってます!何とかしてください!」
- OK例: 「今、チームの業務プロセスで少し非効率になっている点があり、改善のご相談です」
あくまで「チームの生産性向上のための前向きな相談」というスタンスで臨むのがポイントです。
ステップ3:事実と影響、そして改善案をセットで伝える
準備した事実を基に、以下の構成で話を進めます。
- 事実(Fact):
- 「〇〇さんの△△という業務で、最近このようなミスが続いており、そのフォローに毎月約〇時間ほどかかっている状況です」
- 影響(Impact):
- 「その結果、私が担当している□□のプロジェクトの進捗に、若干の遅れが出てきてしまっています」
- 提案(Proposal):
- 「つきましては、〇〇さんの業務チェック体制を見直す、あるいは業務マニュアルを再整備する、といった対策をご相談できないでしょうか」
このように、問題点だけでなく、具体的な改善案までセットで提示することで、あなたがチーム全体のことを考えている建設的な人材であることをアピールできます。上司としても、具体的なアクションを考えやすくなるでしょう。
この戦略的な相談は、状況を動かすための最も効果的な手段の一つです。一人で抱え込まず、上司をあなたの最強の味方につけましょう。
「ここまでしかやらない」物理的な境界線を引く勇気
コミュニケーションによる改善を試みても、相手が変わらなかったり、状況が改善しなかったりする場合も残念ながらあります。そんなときに有効なのが、物理的・時間的な境界線(バウンダリー)を明確に引くことです。
これは「冷たい態度をとる」ということではありません。「自分の責任範囲と他人の責任範囲を明確にし、自分のリソース(時間・労力)を守る」という、プロフェッショナルな行為です。
1. 自分のタスクを可視化し、優先順位を共有する
まず、あなた自身が抱えている全てのタスクをリストアップし、それぞれの優先順位を明確にします。そして、そのリストを上司やチームメンバーに見える形で共有するのです。
- 共有方法: 朝会や夕会で「本日の私の優先タスクはAとBです」と口頭で宣言する
これにより、「あなたが多くの仕事を抱えている」という事実が周囲に客観的に伝わります。その上でフォローを依頼された際に、「申し訳ありません、今はこのタスクが最優先なので、それが終わり次第であれば…」と、正当な理由をもって断りやすくなります。
2. 「安請け合い」をやめる
仕事ができない人からの曖昧な依頼に対して、「わかりました、やっておきます」と即答するのは今日からやめましょう。代わりに、以下の質問を投げかける癖をつけます。
- 「その仕事の目的とゴールは何ですか?」
- 「締め切りはいつですか?」
- 「どこまで私が担当すればよいでしょうか?」
これらの質問をすることで、相手に仕事の責任感を促すとともに、あなたが引き受ける範囲を限定することができます。曖昧な依頼を安請け合いすることは、相手の成長の機会を奪い、あなたへの依存度を高めるだけです。
3. 「定時で帰る」ことを習慣にする
「フォローが終わらないから残業する」というループを断ち切りましょう。勇気を出して、定時で仕事を切り上げる日を作ってみてください。
もちろん、最初は周囲の目が気になるかもしれません。しかし、あなたが定時で帰ることで、「あの人は無限に働いてくれるわけではない」という事実が周囲に伝わります。そして、「自分たちの仕事は自分たちで時間内に終わらせなければならない」という意識がチームに芽生えるきっかけにもなり得ます。
物理的な境界線を引くことは、最初は少し勇気が必要です。しかし、この一歩が、あなたを際限のないフォロー地獄から救い出し、健全なワークライフバランスを取り戻すための大きな転換点となるでしょう。
イライラをリセット!仕事中にできる心を保つ応急処置

どれだけ論理的に対処しようとしても、日々の業務の中でイライラやストレスが溜まってしまうのは避けられないことです。大切なのは、そのネガティブな感情を溜め込まず、こまめにリセットする習慣を身につけることです。
ここでは、仕事の合間に誰にも気づかれずに実践できる、心を穏やかに保つための簡単な応急処置を5つ紹介します。
- 1. 6秒ルール(アンガーマネジメント)
- カッとなったとき、怒りのピークは長くても6秒と言われています。イラっとしたら、心の中でゆっくり6秒数えてみてください。それだけで、感情的な言動をぐっと抑えることができます。
- 2. トイレや給湯室で物理的に離れる
- ストレスを感じる相手や状況から、一時的に物理的な距離を取るのは非常に効果的です。席を立ち、トイレで深呼吸をしたり、給湯室で一杯の水を飲んだりするだけで、気分転換になります。
- 3. 「グラウンディング」で意識を「今」に戻す
- イライラしているとき、意識は過去の失敗や未来の不安に向きがちです。意識を「今、ここ」に戻す「グラウンディング」を試してみましょう。
- ✅ 足の裏の感覚に集中する
- ✅ デスクの冷たさを手で感じる
- ✅ パソコンのファンの音に耳を澄ます
- 五感に意識を向けることで、頭の中のモヤモヤから抜け出しやすくなります。
- イライラしているとき、意識は過去の失敗や未来の不安に向きがちです。意識を「今、ここ」に戻す「グラウンディング」を試してみましょう。
- 4. ポジティブな事実を探す
- 「最悪だ」と感じたときこそ、意識的にポジティブな側面を探してみましょう。「このミスのおかげで、業務マニュアルの弱点が見つかった」「この経験を次に活かそう」など、小さなことでも構いません。物事を多角的に見る癖をつけることで、ストレス耐性が高まります。
- 5. デスクに「癒しグッズ」を置く
- お気に入りのキャラクターの小さなフィギュア、手触りの良いハンドクリーム、好きな香りのアロマストーンなど、見るだけで、あるいは使うだけで少し気分の上がるものをデスクに置いておくのもおすすめです。視覚や嗅覚から、手軽にリフレッシュできます。
これらの応急処置は、根本的な問題解決にはなりませんが、あなたの心が折れてしまわないように守るための大切なクッションの役割を果たします。ストレスはゼロにはできません。だからこそ、「ストレスと上手に付き合う技術」を身につけることが、長期的に働き続ける上で非常に重要なスキルとなるのです。
もう我慢しない!先輩・同僚への賢い関わり方とは?

フォローの対象が、注意しづらい「先輩」や、関係性を悪化させたくない「同僚」である場合、対処はさらに難しくなります。しかし、我慢し続けるのは得策ではありません。相手との関係性を維持しつつ、自分の負担を減らすための「賢い関わり方」が存在します。
ケース1:仕事ができない「先輩」への対応
先輩に対して、正面から「やり方が違います」と指摘するのは角が立ちます。そこで、「教えてください」というスタンスで関わるのが有効です。
- 質問形式で気づきを促す
- 「先輩、この業務のこの部分なのですが、私は〇〇という手順で進めようと思うのですが、先輩のやり方だともっと良い方法がありますか?教えていただけますか?」
- このように聞くことで、相手のプライドを傷つけずに、正しい手順や改善点について一緒に考えるきっかけを作ることができます。
- 感謝と尊敬の念を忘れない
- たとえ仕事ができなくても、あなたより長く会社にいる先輩です。「いつもありがとうございます」「勉強になります」といった言葉を添えるだけで、関係性は大きく変わります。
ケース2:仕事ができない「同僚」への対応
同僚の場合は、ライバル心や遠慮から、かえって本音を言いにくいことがあります。重要なのは、「個人」対「個人」ではなく、「チーム」の問題として捉えることです。
- 「私たち」を主語にする
- 「このままだと、私たち二人の評価が下がっちゃうかもしれないから、一緒にこの業務の進め方を見直さない?」
- 「私たち」を主語にすることで、連帯感が生まれ、協力して問題解決にあたる仲間であるという意識を共有できます。
- 得意なことで役割分担する
- その同僚にも、何か一つくらいは得意なことがあるはずです。「〇〇さんは資料のデザインが上手いから、そっちをお願いできないかな?その分、私がこっちのデータ分析をやっておくから」というように、お互いの強みを活かせる形で業務を分担するのも良い方法です。
どちらのケースにも共通するのは、相手を変えようとするのではなく、関わり方を変えるという視点です。あなたはカウンセラーでも教育係でもありません。相手の成長にまで責任を負う必要はないのです。あくまで自分の仕事が円滑に進む範囲で、ストレスの少ない関わり方を見つけていくことが、あなた自身を守るための賢い選択と言えるでしょう。
全ての対処法が無理なら…環境を変えるという選択肢
ここまで、様々なコミュニケーション術や上司への相談方法、セルフケアなど、今いる環境で状況を改善するための具体的な対処法を紹介してきました。
しかし、もしこれら全てを試しても、
- 上司が全く動いてくれない
- 会社の体質が古く、改善が見込めない
- フォローによる心身の不調がすでに限界に来ている
という状況であれば、最後の、そして最も強力な選択肢として**「環境を変える」、つまり転職を視野に入れること**を真剣に考えるべきです。
一つの会社で我慢し続けることが、必ずしも美徳ではありません。あなたの能力や責任感は、もっと正当に評価され、健全な環境で発揮されるべきです。
転職を考えるべき3つのサイン
- 体調に異変が出ている
- 頭痛、腹痛、不眠、食欲不振など、ストレスが原因と思われる身体的な症状が出ている場合。
- 仕事のことを考えると涙が出る、動悸がする
- 出勤前や、仕事のことを思い出すだけで強い精神的苦痛を感じる場合。
- プライベートの時間が楽しめない
- 休日も仕事の疲れや不安で頭がいっぱいで、全く心が休まらない状態が続いている場合。
これらのサインは、あなたの心と体が「もう限界だ」と叫んでいる証拠です。
おススメの転職サービスはこちら👇
| サービス名 | アルバトロス転職 | ユメキャリ転職エージェント | イーチキャリア |
|---|---|---|---|
| 特徴 | 1. 全国・全職種、常時15万件以上の求人を保有 2. 転職相談から内定までLINEだけでも完結可能 3. 応募した企業の退職代行利用データを無償で開示 | 1. 現役の企業人事が面接や書類選考対策を直接サポート 2. 転職者の職種や業種に詳しいキャリアアドバイザーが専任で担当 3. 企業との交渉も全て代行可能 | 1. 未経験からの転職支援に強い 2.歴や職歴よりも、やる気・向上心・柔軟性を重視したマッチングを実施 3. 入社後の定着フォローまで、きめ細やかなサポート体制 |
| リンク先 | 無料の会員登録はこちら | 大手企業の現役面接官が運営する転職エージェント【ユメキャリAgent】 無料相談はこちら👆 | 無料の会員登録はこちら |
転職活動は「ノーリスク」な情報収集
「転職」と聞くと、ハードルが高いと感じるかもしれません。しかし、すぐに会社を辞める必要はないのです。まずは転職エージェントに登録し、今のあなたが転職市場でどのような評価を受けるのか、どのような会社があるのか、といった情報を集めるだけでも、大きな価値があります。
転職エージェントは、あなたのキャリアの棚卸しを手伝ってくれたり、非公開の優良求人を紹介してくれたりする、キャリアのプロです。相談するだけでも、今の会社を客観的に見る良い機会になります。
「今の会社にしがみつかなくても、自分には他にも選択肢がある」
この事実を知るだけで、心に大きな余裕が生まれます。その余裕が、今の職場での立ち振る舞いを変え、事態が好転するきっかけになることさえあります。
もし、心身の限界から「明日からもう会社に行けない」という状況であれば、退職代行サービスを利用するのも一つの手段です。あなたに代わって、退職の意向を会社に伝えてくれます。
あなたの人生は、今の会社だけではありません。自分を大切にするための最後の切り札として、「環境を変える」という選択肢を常に持っておいてください。
おススメの退職代行サービスはこちら👇
| サービス名 | 労働組合運営の退職代行ネルサポ | 退職110番 | 退職代行モームリ |
|---|---|---|---|
| 特徴 | 1. 業界最安値級の料金設定(追加料金なしで退職成功率100%の実績がある人事のプロが円満退職をサポート) 2. 回数無制限の無料相談(退職心理カウンセラーが在籍、退職後も回数無制限で無料相談が可能) 3. 労働組合が運営(弁護士法違反の心配なしで会社との交渉が可能) | 1. 社会労務士および弁護士資格を有する為、様々な労働問題に関する知見・ノウハウを有し、法律上のトラブルに対してもしっかりと対応が可能 2. 未払い金請求や慰謝料請求など、各種請求・交渉に完全対応 3. 会社に対して賠償請求をしたい方におススメ | 1. 累計4万件以上の退職を確定させた実績とノウハウ(相談実績は7万件) 2.お支払いに2種類のあと払いが可能、代行サービス利用後は1年間は当社再利用50%off 3. 退職できなかった場合の全額保証及び退職や勤務に関しての相談は何度でも何時間でも無料 |
| 料金 | 税込み15,000円 | 税込み43,800円 | 税込み22,000円 税込み12,000円(アルバイトの方) |
| リンク先 | ご相談・申込はこちら | 無料相談・申込はこちら |
まとめ|仕事できない人のフォローに疲れる悩みを解決しよう

この記事では、「仕事できない人のフォローに疲れる」という深刻な悩みについて、その原因から具体的な対処法までを深掘りしてきました。
最後に、重要なポイントをもう一度おさらいしましょう。
- 疲れの原因はあなただけじゃない
- あなたの疲れは、個人の問題だけでなく、不公平な業務分担、マネジメントの不在、会社の構造的な問題など、様々な要因が複雑に絡み合って生じています。
- 「疲れた」と感じるのは、甘えではなく当然の感情です。
- まずは自分を守ることから始める
- あらゆる対処法の基本は「自己防衛」です。罪悪感を手放し、自分の心とキャリアを最優先に考える許可を自分に出しましょう。
- 具体的なアクションプラン
- コミュニケーションを変える: IメッセージやDESC法を使い、角を立てずに自分の状況を伝える。
- 上司を味方につける: 感情ではなく事実に基づき、改善案をセットで戦略的に相談する。
- 境界線を引く: 自分のタスクを可視化し、安請け合いをやめ、物理的な線引きを行う勇気を持つ。
- セルフケアを怠らない: イライラをこまめにリセットする応急処置を身につける。
そして、これらの対処法を尽くしても状況が改善せず、あなたの心身が限界に達しているのなら、ためらわずに「環境を変える」という選択肢も検討してください。
今の職場が、あなたのすべてではありません。あなたの頑張りや能力は、もっと正当に評価され、気持ちよく働ける場所でこそ輝きます。
この記事が、際限のないフォロー地獄に苦しむあなたの心を少しでも軽くし、次の一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。もう一人で抱え込まず、あなた自身の未来のために、今日からできることを始めてみましょう。
-

-
転職の証明写真はブラウスが無難?|襟あり・なし・色ガイド
2025/9/7